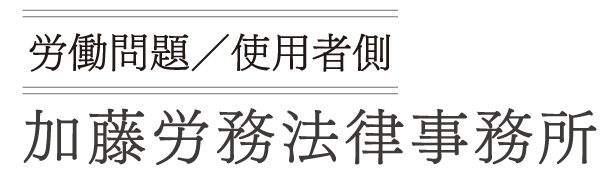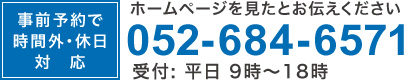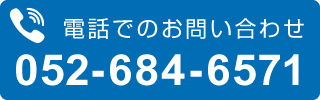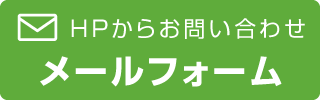Archive for the ‘ブログ(業務にお役立てください。)’ Category
労働審判期日(第1回期日)の実際【会社向け】
今回は、実際の労働審判期日について、ご説明します。
参加者
裁判所:労働審判官1名(裁判官)、労働審判員2名(使用者側・労働者側)
申立人:申立人(本人)、申立人代理人(弁護士)
相手方:会社担当者(社長・人事担当者など)、関係者(上司、同僚など)、相手方代理人(弁護士)
会社の立場で言いますと、「関係者(上司、同僚など」の参加は必須です。
関係者が参加しないと、客観的証拠がない限り、事実関係に関する会社側の主張を裁判所に認めてもらうことはできません。実務を経験すると、「客観的証拠」と言っても、「誰が見ても会社の言い分が証明される明白な証拠」というものはほとんどなく、提出した証拠(書類、メールなど)について、作成目的・作成経緯・作成前後の状況など、裁判所からの確認があると考えてください。
また、労働事件は、労使間のトラブルが数か月(場合によっては数年単位)で続いてきたケースが大半です。そして、長期にわたる事実経過の中で、「客観的証拠」(書類・メールなど)が全て揃っているケースは稀です。このため、関係者による事実関係の説明が不可欠です。
さらに、労働審判期日には、申立人(労働者)が参加して、自らの言い分を裁判所へ直接説明します。しかし、その説明の中には、会社からみると「事実とは認め難い」内容もあります。そのような場合に、キチンと反論するためには、その件に直接関与していた人物(=上司・同僚などの関係者)が労働審判期日に出席し、会社側の言い分をしっかりと裁判所へ伝える必要があります。
事実関係の確認
裁判所は、あらかじめ「労働審判申立書」と「答弁書」をよく読んだうえで期日に臨んでいます。このため、裁判所からは、双方が主張する事実関係について、申立人・相手方双方に対し、かなり突っ込んだ質問があります。
例えば、以下のような質問です。
「ここに○○と書いてありますが、具体的にはどのようなことがあったのですか?」
「甲○号証(証拠)には、『△△』と書いてありますが、これはどういう意味ですか?」
「(証拠を示しながら)どうしてこのような書類を作成したのですか?」
「(関係者に対し)先ほど、申立人が『××』と言っていましたが、そのような事実はありましたか?」
など、「答弁書に書いていないこと」や「答弁書では、はっきりしないこと」を中心に質問されると考えてください。また、提出した証拠の内容についても質問されると考えておいてください。
以上の質問は、関係者本人でないと回答できません(人事担当者は「当事者からの伝聞」が多く、しかも、細かい点まで把握できていないことから、しっかると回答できない可能性があります。)。
さらに、裁判所は、関係した当事者本人に質問し、その回答を求める傾向が強いといえます。
当事者本人であっても回答に窮する場合があり、たまに代理人が助け舟を出すこともありますが、基本的には関係者本人が回答しなければなりません。
したがって、期日当日は、関係者(上司、同僚など)の出席が不可欠です。
そして、ここでキチンと説明・回答できるか否かが結論に大きな影響を与えます。
なお、このような事実関係の質問は、申立人と相手方の双方に行われます。
事案にもよりますが、争点が多岐にわたる場合(懲戒解雇の事案で、労働者の問題行動が多い場合など)は、それぞれ1時間前後(場合によっては、それ以上)の時間がかかると思ってください。
和解に向けた協議
双方からの事実関係の聴取が終わると、和解に向けた協議が行われます。
労働審判は、調停による解決(和解)を前提とした手続であるため、このような協議の席が設けられます。
事実関係の確認は、当事者(申立人・相手方)が同席した状態で行われますが、和解に向けた協議は、申立人と相手方が別々に裁判所と話します。
和解に向けた協議の席では、裁判所から和解解決に向けた考えについて質問されます。
このため、労働審判期日に先立ち、和解する場合の条件(解決金の金額など)について、社内や弁護士との間で協議しておく必要があります。
このとき、裁判所から事案に関する裁判所の考え(心証)が開示され、裁判所が妥当と考える和解案が提示されることになります(申立人の希望が伝えられることもあります。)。これに対し、会社側として、「譲歩できるところ・できないところ」を明らかにして、譲歩できるところは「どこまで譲歩できるか」を裁判所に示します。
このような裁判所とのやりとりを申立人・相手方がそれぞれ行い、和解解決による解決の可能性を探ることとなります。
なお、労働審判の場合、第1回期日で和解できるケースも多いため(裁判所もそのようなスタンスで当事者に対応します。)、可能であれば決裁者の同席が望ましいと言えます(同席が困難である場合には、決裁者と連絡がとれる状態にしておく必要があります。)
その場で即答できない場合は、第2回期日を入れることになります(なお、第2回期日以降は、和解に向けた協議が中心です。)。
最後に
労働審判期日の実際は、以上のとおりです。
「裁判」というと、弁護士が活躍するイメージがありますが、労働審判期日の主役は当事者(申立人本人・上司や同僚などの関係者)です。
「答弁書に書いてもらったから大丈夫」と考えてはいけません。
しっかりと準備して、期日当日に臨んでください。
【関連ブログ】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
労働審判で会社が準備すべきこと【会社向け】
労働審判は、原則として3回以内の期日で審理を終結することになっています。もっとも、ほとんどのケースでは、第1回期日の段階で、裁判所が具体的和解案を提示します。このため、労働審判は「第1回期日が勝負」です。したがって、従業員から労働審判を申し立てられた場合、会社は、直ちに対応準備に取り掛からないといけません。
今回は、労働審判を申し立てられた場合の会社の初動対応について、ご説明します。
事実関係の整理(時系列にまとめる。)
労働審判を申し立てられた場合、会社だけで対応することは事実上不可能です。弁護士に依頼して、会社の言い分を裁判所にきちんと伝える必要があります。そして、そのためには、まずは弁護士に、事実関係を正確に伝えなければなりません。
これまでの経験上、弁護士に事実関係を正確に伝えるためには、次の点に注意していただくのがよいと思います。
まずは、労働審判申立書を読んでください。そして、従業員が何を要求しているかを確認してください。また、労働審判申立書には、申立てに至る事実経緯が記載されています。これに対し、会社側の言い分を時系列に沿って作成してください(簡単なもので構いません。)。
事件の類型によって、重要となる証拠・ポイントは、次のとおりです。
① 退職が争われるケース(不当解雇)
退職時に本人が提出した書面があるかを確認するとともに(退職届など)、関係者(上司、同僚など)から退職に至る経緯を聴取してください。なお、退職に至る過程でメールのやりとりをしている場合も多いので、メールも確認してください。
② パワハラが争われるケース
通常であれば、労働審判を申し立てられる前に、従業員(申立人)からパワハラ被害に関する申告があったはずです。そのときの調査結果を確認するとともに、労働審判申立書に記載された内容を踏まえ、再度、関係者に聴取してください。
③ 残業代請求の場合
労働時間に関する資料(勤怠記録など)を確認するとともに、給与計算の内容について社会保険労務士(社労士)に確認してください(給与計算を社労士に依頼している場合)。
なお、早い時点で弁護士に委任することができた場合には、関係者への聴取の際、弁護士にも同席してもらいましょう。そうすることで、準備と時間が節約できます。
速やかに弁護士へ相談・依頼すること
労働審判申立書に対する反論書の提出期限は、日程がタイトです。そこで、上記の調査と並行して、弁護士に相談し、速やかに依頼してください。
労働審判は裁判に準じた手続であり、専門的な知識・経験がないと対応できません。「自社で何とかなるだろう。」と考えてはいけません。
依頼する弁護士が見つかった場合には、早急に弁護士と打合せを行ってください。このとき、事実関係を時系列に沿って整理していると、弁護士もスピーディーに事案を理解することができます。また、労働審判では、会社側の証人として関係者(上司や同僚など)が同行し、裁判所に事実関係を説明する必要があります。会社側証人を決めるためにも、弁護士との打合せはただちに実施する必要があります。
最後に
労働審判を申し立てられた場合の初動対応についてご説明しました。この手続は、「第1回期日が勝負」です(第1回期日で裁判所から和解案が提示されるケースが大半です。)。そこで、裁判所から労働審判申立書が届いたら、速やかに対応することが重要です。
加藤労務法律事務所は、これまで会社側代理人として多数の労働審判事件を取り扱っており(解雇事件・内定取消事件など)、ポイントを押さえた準備・書面作成・期日対応を行います。労働審判を申し立てられた企業様は、加藤労務法律事務所へご相談ください。
→ お問い合わせは、こちらまで(お問い合わせ画面に移動します)
【関連ブログ】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
退職勧奨の面談準備(想定問答)【会社向け】
問題社員の退職勧奨を行う際、「何を聞かれるか」、「どのように答えるか」、「どのように言えばいいのか」など、面談前に想定問答集を準備しておくことは非常に大切です。
当日のやりとりを全て事前に準備しておくことは不可能ですが、ある程度のところを準備しておくことは可能です。今回は、退職勧奨を行うにあたり、面談前に準備しておくべきポイントや退職勧奨の切り出し方について、説明します。
1 想定問答集の準備
部下・従業員に対する退職勧奨を行うことは、ご担当者様(上司や人事担当者など)にとってもストレスの大きい業務です。あらかじめ想定問答集を作成して協議に臨むことができれば、ご担当者様の精神的負担を軽減させることができます。
退職勧奨の場合には、以下の点について、想定問答を準備しておくとよいでしょう。
① どのような会話から始めるのか。
② どのように退職の話を切りだすのか。
③ 本人から「クビですか?」と言われた場合の回答
④ 「辞めたくない」と言われた場合の回答
⑤ 退職金、有給消化、雇用保険、健康保険に関する回答
これらの点について、想定問答を一言一句準備することはできません。「こんな感じのことを聞かれたら、こう答えよう」程度の準備で十分です。
また、対象者から、想定外の質問や回答が出てくることも予想されます。もし、そのような質問や回答が出た場合で、その場で対応できないものについては、「宿題」として持ち帰り、いったん交渉を終えることも重要です。想定外の質問に対し、回答をはぐらかしたり、無理に押し切ろうとしたりすると、対象者は不信感を抱き、トラブルに発展する危険があります。
2 退職勧奨の切り出し方
会社が退職勧奨を行うのは、その従業員が問題行動に及んだことが理由と考えられます(しかも、会社が退職勧奨を行うくらいですから、問題行動を繰り返していると思われます。)。
そこで、「本人の問題行動→会社による注意指導→問題行動が改善しなかったこと」を具体的に説明できるよう準備してください。そして、問題行動に関する対象者の自覚や反省、今後、同種行為に及ばないよう、どのような点に注意するかを聴取してください。その際は、問題行動に関する対象者の考えをしっかりと聞くことがポイントです。
対象者の考えを聞いたものの、「今後、気を付けます」といった程度の回答しか返ってこない場合もあります。
しかし、問題行動を起こしている以上、このような回答では不十分です。「今後、どのような点に気を付けるのか」、「そのために、今からどのような対応・対策をとるのか」等、具体的な再発予防に向けた考えを聞いてください。
再発予防策について具体的な回答を求めることは、他の社員に対する安全配慮義務や企業秩序維持(円滑な業務遂行)のためにも必要です(例えば、パワハラのケースなど)。
上記の質問に対し、本人が話をそらそうとする、本人から十分な回答を得ることができない場合には、本人は自らの問題行動を自覚していないと思われます。会社が退職勧奨を検討するケースは、多くの場合、対象者が過去にも同種行為を行っていると考えられるため、再び問題行動を起こす可能性は非常に高いと考えられます。
しかし、仮に、問題行動を繰り返した場合、職場内の人間関係がギクシャクする等、対象者にとっても働きにくい状況になることが予想される。そうであれば、ここで退職することも選択肢の一つではないかと提案するのが自然な流れといえます。
また、本人が「問題行動を起こしたことを他の従業員のせいにすること」も想定されます。
このような場合には、複数の従業員(上司)が本人に対応したものの、いずれも同じ結論(人間関係のトラブル等の問題が発生したこと)になっている事実、他の従業員はそのようなトラブルが起こっていないことを淡々と説明することが考えられます。
これらの説明を通じて、その会社で働き続けることは、今後も職場内での人間関係のトラブルが生じる可能性があることが浮かび上がります。そして、そのような状況で働き続けることは対象者にとっても本意ではないと思われ、そうであれば、会社を退職し、別の会社で働くことも選択肢の一つではないかと提案することになると考えられます。
3 本人から「クビですか?」と言われた場合の回答
退職勧奨を行う場合、対象者から「クビですか?」と言われることが多いです。
「クビ」とは、「解雇」を意味します。解雇するか否かは会社が決めることです。これに対し、退職勧奨は、会社を辞めるか否かは対象者本人が決めます。したがって、退職勧奨に対し、「クビですか?」と問われた場合は、「クビ(=解雇)ではない」旨を説明してください。
退職勧奨は、会社における対象者の状況を考えると、このまま会社に居続けることは、客観的にみて、会社(他の従業員)と対象者本人の双方にとって望ましいとはいえないと考えられるため、将来の選択肢の一つとして「退職」を提案するものに過ぎません。退職勧奨は、このような事情を丁寧に説明することになります。
重大な懲戒事由があり、本来であれば懲戒解雇が相当なケースは、温情的な措置として退職を勧めることもあります。この場合、退職勧奨を拒否した場合には、懲戒解雇を検討することになりますが、そのような事情がない場合、本人から退職する気がないと告げられたにもかかわらず、執拗に退職を迫ることは違法と判断される可能性があります。
【関連ブログ】
退職勧奨を「パワハラ」と言われないようにするための注意点【会社向け】
違法な退職勧奨と言われないようにするための注意点【会社向け】
会社が解雇通告する前に検討すべきこと(解雇に潜むリスク)【会社向け】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
労災による賠償請求があったときに検討すべきこと(被災者側の減額事由)【会社向け】
過重労働が原因で脳出血や心筋梗塞などの疾病が発症したとします。この場合、会社は被災者に対し、安全配慮義務違反による損害賠償義務を負うこととなります。しかし、被災者が高血圧であった、あるいは、飲酒・喫煙習慣があった等、疾病の原因となる基礎疾患や生活習慣を有していた場合、これらの点は、どのように取り扱うことになるでしょうか。今回は、被災者側の減額事由について、ご説明します。
1 被災者側の減額事由
被災者が過重労働等の業務に起因して脳出血や心筋梗塞などの疾病を発症した。他方で、その被災者には、高血圧の治療歴や飲酒・喫煙の生活習慣があった。
この場合、被災者が疾病を発症したのは、過重労働(会社の安全配慮義務違反)と既往症・生活習慣(被災者側の事情)が競合した結果と考えることができます。仮に、被災者側にこれらの事情がある場合には、疾病を原因とする被災者の損害について、その全てを会社に負担させることは当事者間の公平に欠ける結果となりかねません。つまり、被災者側に基礎疾患や生活習慣がなければ、ここまで損害が大きくならなかったといえる場合には、損害の全部について、会社に賠償責任を負わせるのが正しいか、ということです。
労災による損害賠償が争われる場合には、このような観点から、会社の被災者に対する損害賠償責任について、一定割合の減額がされる場合があります。
例えば、長時間労働によって疾病が発症したケースにおいて、被災者の生活習慣(飲酒・喫煙習慣)、持病の治療を受けていなかった点を踏まえ、会社側が負担すべき損害額が減額された事案も存在します。
2 実務上の注意点
以上が原則です。
ところが、実務では、被災者側の事情を「立証」(証明)しなければならないというハードルが存在します。つまり、抽象的に、「飲酒習慣があった。」、「喫煙習慣があった。」、「高血圧であった。」等と言うだけでは、裁判所は取り上げてくれません。
したがって、これらの事情をいかにして立証するかが重要となりますが,実は,この立証問題が難しいのです。
過去に取り扱ったケースでは、被災者本人のカルテを取り付けたところ、本人自筆の問診票に基礎疾患に関する記載(高血圧の治療歴)や生活習慣に関する記載(ヘビースモーカーであったこと)があったため、これらを証拠提出したところ、減額事由となる被害者側の事情が認定され、一定割合の減額が認められたことがあります。
3 まとめ
先般、高年齢者雇用安定法が改正されたことに伴い、今後、高齢労働者が就労する機会は、さらに増えていくでしょう。年齢を重ねるほど、高血圧などの基礎疾患を抱える人は増え、脳出血などの発症リスクは高まると考えられます。そして、脳出血等の疾病が発症した場合、労災であると主張されるリスクは高いと予想します。
このような主張を防止するためには、まずは長時間労働を抑制することが重要です。さらに、賠償額の適正化という観点から、労働者の健康管理の重要性は、ますます高くなると考えます。
【関連ブログ】
労災による損害賠償請求を受けた場合に、まず行うこと【会社向け】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
労災による損害賠償請求を受けた場合に、まず行うこと【会社向け】
労災事故が発生し、被災者(従業員)が労災認定された。この場合、会社は、被災者から安全配慮義務に違反したとして、損害賠償請求を受けることがあります。今回は、そのような請求を受けた場合に、まずは会社が行うべきことについて、ご説明します。
1 労災事故を理由とする損害賠償請求
労災事故が発生し、被災者が労災認定された。この場合、会社は、被災者から、労災保険給付では補償されなかった損害について、多額の損害賠償請求を受けることがあります。
この場合、どのように対応すればよいでしょうか。
2 まずは、弁護士に相談すること
被災者(実際は、その代理人弁護士)から損害賠償請求の書類が届いたら、まずは弁護士に相談してください。その際、労基署に提出した労働者死傷病報告や労災申請の関係で提出した書類の控えがあれば、それを持参してください。また、社内で労災事故を調査していれば、それらの資料も持参してください。
これらの資料があれば、相談を受けた弁護士は、事故状況、被災者の怪我の程度など、事案の概要を把握できます。例えば、後遺障害が残存したとして、逸失利益や後遺障害慰謝料の請求があった場合、認定された後遺障害の内容・程度によって、これらの損害(逸失利益・後遺障害慰謝料)の概算額を計算して、請求額の妥当性を検証することが可能となります。
3 事故状況の把握
事故状況は、被災者にも過失があったといえるかを検討する材料となります。例えば、被災者が構内ルールを守らなかった結果、事故に遭ったのであれば、被災者の過失を問える可能性があります。この場合、過失相殺の主張(被災者の過失分は自己負担すべきとの主張)が可能となります。
仮に、過失相殺の主張ができるのであれば、これにより、賠償額の圧縮を図ることが可能です。例えば、被災者の過失割合が20%の場合、総損害の20%を控除できることになります(総損害が1000万円の場合、そこから200万円を控除できることになります。)。
被災者は、過失相殺をしないで損害賠償請求することが多数あります。しかし、実際は、過失相殺できる場合もありますので、事故状況に関する資料は非常に重要です。
4 怪我の程度の確認
被災者の怪我の程度(特に、事故当初の怪我)の程度を確認することも重要です。例えば、軽傷事案(打撲など)であるにもかかわらず、休業期間が長期化していた場合、被災者が請求する休業損害は過大であり、その全てを賠償する必要はないと主張できる可能性があります。また、怪我と比べて休業期間が長いと思われる場合には、労災事故による怪我だけでなく、別の要因も相まって長期化したのではないかと考えることもできます。
後遺障害が残存した場合には、当初の怪我と認定された後遺障害との間に整合性があるかも重要なポイントです。労災事故による怪我と既往症(事故前からの持病など)が相まって後遺障害が残った場合には、後遺障害に関する損害(逸失利益、後遺障害慰謝料)について、一定割合の減額主張が可能となる場合もあります。この点については、過去の裁判例を参考に、① 減額できるか否か、② 減額できるとして、どれくらい減額できるか、を検討することになります。
これらについては、「労災に関する知識」のみならず、「損害賠償の裁判実務に関する知識・経験」が必要な分野です。
5 まとめ
今回は、会社が被災者から損害賠償請求を受けた場合に、まずは行うべきことをご説明しました。 多額の損害賠償請求の書類を受け取ると、驚きのあまり、何をすればよいか分からず、途方に暮れるかもしれません。でも、皆さんの会社の味方となってくれる人は必ずいます。今回のブログを参考に、やるべきことを一つずつ実行してください。
【関連ブログ】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
退職勧奨を違法と判断した裁判例【会社向け】
今回は、上司らの退職勧奨が違法であり、不法行為と判断された裁判例を紹介します(宇都宮地裁令和2.10.21)。退職勧奨を行う際には、参考にしてください。
1 事案の概要
バスの乗務員(運転手)である原告が、上司である被告らから退職強要や人格否定等のパワーハラスメントを受けたとして、慰謝料を請求したケースです。
原告は、乗客に対する接客態度に問題があったとして(←複数回あったようです。)、複数の上司から長時間(約1時間)にわたり退職するよう繰り返し迫られ、その後、「うつ状態」となりました。
2 裁判の判断
裁判所は、原告が辞めたくないと述べたにもかかわらず、3日間にわたり、複数の上司らが原告に対し、次のような発言に及んだことは、退職勧奨として許される限度を逸脱したものであり、不法行為が成立すると判断しました(なお、違法な退職勧奨のほか、パワハラもあったとして、慰謝料は60万円と認定されました。)。
① 「もう二度とバスには乗せない。」
「もう終わりです。」
→ 運転業務がない中で、バスに二度と乗せない旨を表明したこと
② 「その辺のチンピラがやることだよ。チンピラはいらねんだようちは。」
「雑魚はいらねえんだよ。」
「まあもう会社ではいらないんです。」
→ 会社には要らない旨を繰り返し告げたこと
③ 「うちの会社には向かねえよこんな会社って、見切りをつけて他の会社行けよ。」
「どっかへ行けよ。それを言ってんだよ。」
→ 他の会社へ行けと言ったこと
④ 「一身上の都合で円満にあれしたほうがよろしいんじゃないかと。」
「円満のがいいでしょ?だってその方が、今度ね他へ就職するにしても」
→ 自主退職すべきことをほのめかしたこと
⑤ 「じゃあ、書けよ・・・。書けよ。」
「退職願を」
→ 退職願を書けと命じたこと
3 本件の特徴
「もう二度とバスには乗せない。」、「チンピラはいらねんだよ。」、「どっかへ行けよ。」、「(退職願を)書けよ。」など、上司らの発言は、原告に退職を促す、あるいは、退職するよう説得するものではなく、退職を強要する内容といわざるを得ません。しかも、本件では、3日間という短期間に、複数の上司が原告一人に対し、上述した発言を繰り返していた点が特徴的です。
また、判決では、上司らの発言が細かく認定されています。これは、原告が発言内容を録音し、それを証拠提出されたことが理由と考えます。
4 まとめ
本件では、原告の接客態度に問題がありました。しかも、過去に同様の問題があったようです。だから、上司らは、原告にはバスを運転させられないと考えて、退職勧奨に及んだと考えます。
もっとも、原告の接客態度は問題があったものの、解雇相当といえるほどの重大なものではなく、そもそも退職を強く勧めることはできないケースであったと考えます。
このようなケースでは、まず、問題行動について懲戒処分(戒告・減給・出勤停止など)を検討します(無理に退職させようとしない。)。そして、その過程で、本人に接客態度に問題があることを自覚させます。そのうえで、退職勧奨する場合には、バス乗務員は接客が不可欠であるため、接客態度が改まらないのであれば、バス乗務員は向いていないのではないか、といった趣旨の発言にとどめるべきであったといえます。
これに対し、本件は、「退職勧奨」といいながら、「どうしても退職させよう」とした結果、言い過ぎてしまい、不法行為と認定されてしまいました。このようなケースは、たまに見られるケースなので、ご注意ください。
なお、本件では、原告が上司らの発言を録音していました。退職勧奨の場面では、このように従業員が担当者の発言を録音しているケースは非常に多くあります。このため、退職勧奨を行う場合には、「従業員に録音されていること」を前提に発言・対応してください。
【関連ブログ】
退職勧奨を「パワハラ」と言われないようにするための注意点【会社向け】
違法な退職勧奨と言われないようにするための注意点【会社向け】
会社が解雇通告する前に検討すべきこと(解雇に潜むリスク)【会社向け】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
会社側からみた労働審判手続の実際【会社向け】
例えば、解雇問題や残業代請求等で、労働者から労働審判を申し立てられたとします。ほとんどの会社は、労働審判を申し立てられたことがないため、実際に、どのような流れで進むかイメージできないと思います。
今回は、そのような会社の皆様に対し、労働審判が申し立てられた場合の実際の手続等について、ご説明します。
1 労働審判とは
労働審判とは、解雇問題や残業代請求などの労使間のトラブルについて、迅速に解決するための手続です。
次の点が特徴です。
① 裁判の場合、裁判官が審理しますが、労働審判の場合、裁判官(労働審判官)のほか労働審判員2名が手続に関与します(その結果、3名で審理することになります。)。
労働審判員は、裁判官ではなく、企業の人事労務や組合活動に携わっていた等、労働問題に関する知識や経験を有する人が任命されます。これらの人々が関与することで、実情に即した解決を図ろうとする趣旨です。
② 労働審判は、原則として3回以内の期日で審理を終結することになっています。もっとも、ほとんどのケースでは、第1回期日の段階で、裁判所が和解案を提示します。このため、労働審判は「第1回期日が勝負」という側面が非常に強い手続です。
③ 労働審判は、裁判所・申立人・相手方が同じテーブルに座り、手続が進行します。裁判所から当事者への質問が多く、当事者は、これらに回答する必要があります。そこで、当事者(関係者)として参加する場合、いろいろな質問が出てくると覚悟して、労働審判期日に臨む必要があります。
2 労働審判の準備
労働審判の準備は大変です。前述しましたとおり、労働審判は、「第1回期日が勝負」であるため、第1回期日に向けて、しっかりと準備する必要があります。
具体的には、当方に非がない旨の言い分(主張)を整理し、その主張に沿った証拠を提出しなければなりません。しかも、書類等の提出期限は、労働審判の書類が届いてから約1か月後であることが多く、日程もタイトです。そこで、労働審判の申立てがあったら、速やかに準備を進める必要があります。
労働審判は、裁判所が法律に基づいて争点(不当解雇であるか、残業代があるか等)を審理します。このため、会社は、「会社の対応は、法的に問題がなかったこと」について、証拠に基づいた主張を行う必要がありますが、このような準備は、事実上、弁護士でなければ行うことができません。
そこで、労働審判の申立てを受けた場合には、資料(証拠)を集めるとともに、速やかに弁護士を探してください。そして、依頼する弁護士が見つかった場合には、早急に弁護士と打合せを行ってください。このとき、会社側で時系列に沿って整理していると、弁護士もスピーディーに事案を理解することができます。
また、労働審判の場合、当該事案の関係者(同僚や上司など)にも労働審判期日に出頭してもらう必要があります。そこで、弁護士と関係者との打合せの日程も確保してください(通常は、事実関係の聴取は何度か行うことになります。)。
3 労働審判期日
事前に主張書面や証拠を提出していても、労働審判期日には、裁判所から事実関係に関する質問があります。そこで、労働審判期日には、関係者も必ず同席してください。関係者が同席しない場合には、申立人側の「言いたい放題」になってしまう危険があるので、ご注意ください。
審判期日は、おおむね2時間を予定してください(なお、和解成立の見込みがある場合には、延長する可能性もあります。)。当日は、裁判所の質問が1~1.5時間くらいあります。そして、質問が一通り終わった時点で、和解に向けた話し合いに移行します。
和解に向けた話し合いでは、申立人と相手方は別々に話を聞かれることになります。このとき、裁判所から、心証が開示されるとともに和解案が提示されます。
労働審判の場合、第1回期日で和解が成立するケースが多くあるため、当日、決裁権者が同行できない場合には、連絡がとれるようにしておいてください。
4 最後に
労働審判手続の実際をご説明しました。繰り返しとなりますが、この手続は、「第1回期日が勝負」です。このため、裁判所から労働審判に関する書類が届いたら、速やかに弁護士に相談し、委任することが重要です。
労働審判を申し立てられてお困りの企業様は、弁護士加藤大喜までご相談ください。
→ お問い合わせは、こちらまで(お問い合わせ画面に移動します)
【関連ブログ】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
会社が解雇通告する前に検討すべきこと(解雇に潜むリスク)【会社向け】
「問題社員を何とかしたい。」と考えた場合。
問題社員に注意・指導を繰り返しても改善しないため、解雇することを考えたとします。
「問題行動や注意・指導に関する証拠は集まった。あとは、解雇するだけ。」このような状況であっても、解雇を通告する前に、まずは「退職勧奨」するのがよいと考えます。今回は、「解雇」に潜むリスクについて、ご説明います。
解雇に関する証拠の収集
① 問題行動を繰り返す社員に対し、注意・指導を繰り返す。
② その際、業務命令書や注意指導書を発行し、場合によっては懲戒処分を行うなど、注意指導に関する資料(証拠)を残しておく。
解雇権を行使するにあたり、会社による解雇が有効であることを裏付ける証拠を積み上げておくことは重要です。
これらが十分に集まっていない状態で解雇すると、裁判で争われた場合、解雇無効と判断されるリスクが非常に高くなります。
解雇に潜むリスク
それでは、解雇に関する証拠が積み上がった場合、解雇権を行使しても全く問題ないでしょうか。
この点については、解雇に潜む次のリスクから、やはり解雇権行使には慎重であるべきと考えます。
裁判所が判断するリスク
会社による解雇が有効であるかについて、裁判で争われた場合、解雇の有効性は裁判所が判断することになります。実は、裁判所が解雇の有効性を判断することは、それ自体、非常に大きなリスクといえます。
裁判所は、法律に基づいて、解雇の有効性を判断します。そして、その法律(労働契約法16条)は、解雇の要件として、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当であること」を要求しています。
しかし、これらの要件は曖昧であり、どのような場合に、「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当である」といえるか判然としません。すなわち、判断する人によって、結論は変わり得るのです(例えば、解雇の有効性については、地方裁判所と高等裁判所で判断が異なるケースは、少なからずあります。)。
このため、会社が証拠十分と判断して解雇しても、裁判で争われた場合には、解雇無効と判断されるリスクは常にあります。
無用な紛争に巻き込まれるリスク
解雇の場合には、解雇が無効であったとの理由で、社員から訴訟提起されるリスクは非常に高くなります。
この場合、会社は、その訴訟に対応せざるを得ず、時間とお金(弁護士費用)を費やすこととなります。しかも、事案によっては、その社員が所属していた部署の別の社員に協力してもらう必要があり、会社の機会損失は大きいといえます。
退職勧奨を検討することの重要性
これらのリスクを考慮すると、解雇権を行使する前に、退職勧奨することがよいと考えます。
退職勧奨に応じてもらい、当該社員から退職届を提出してもらえれば、「解雇」ではなく「自主退職」となります。「自主退職」で処理できた場合には、「解雇」の場合より、後日、社員側から訴えられる可能性は低くなるといえます。しかも、裁判となった場合でも、「解雇」よりも「自主退職」の方が、有効性の立証に関する会社側の負担は少ないといえます。
さらに、問題社員が退職勧奨に応じず、会社が解雇せざるを得なかった場合であっても、このような手続を踏んだ点は、裁判となった場合には、会社側に有利な事情として考慮されると考えます。
以上の理由から、問題行動を繰り返す社員であっても、解雇を通告する前に、退職勧奨を行うのがよいといえます。
【関連ブログ】
退職勧奨を「パワハラ」と言われないようにするための注意点【会社向け】
違法な退職勧奨と言われないようにするための注意点【会社向け】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
問題社員の解雇を検討する際に注意すべきこと【会社向け】
「問題社員を何とかしたい。」というご相談を多数受けます。例えば、「問題社員をどのように注意すればよいか。」や「問題社員に辞めて欲しい。」など。今回は、問題社員の解雇を検討する際の法的注意点について、ご説明します。
1 よくある相談例
よくある相談例として、「問題社員に辞めて欲しいと考えているが、どのように対応すればよいか。」というものがあります。これまでに、どのような注意指導を行ってきたかを確認してみると、「これまでは穏便に済ませようと思い、口頭で注意したくらいです。」という回答が結構あります。
2 「退職」と「解雇」の違い
問題社員に辞めてもらう方法として、「退職」と「解雇」があります。
このうち、「退職」は、「従業員が自発的に会社を辞めること」なので、強制的に「退職」させることはできません。問題社員に退職してもらうために、会社としてできることは、「退職勧奨すること」くらいです。
これに対し、「解雇」とは、会社が従業員に対し、一方的に労働契約の終了を通告する行為です(←「クビ」のことです。)。このため、会社としては、問題社員が「退職」しない場合には、「解雇」できないかを考えます。
3 解雇権濫用の法理
しかし、ご承知のとおり、日本では、会社は従業員を自由に解雇することはできません。法律上、解雇権の行使には厳しい要件が課されています(解雇権濫用の法理:労働契約法16条)。すなわち、「解雇」とは、会社員としての「死刑判決」にほかならないので、「会社が注意指導を繰り返しても改善しなかった。」(もはや解雇以外に採りうる方法がなかった。)といえる状況が必要です。
4 裁判の特徴(特殊性)
会社が解雇すれば、解雇された従業員は、かなりの可能性で解雇無効の訴訟を提起します。裁判の世界では、「客観的証拠」(=書面)が全てです。このため、「口頭注意」のみの場合、従業員側が「注意など受けていなかった。」と否定すれば、裁判所に「会社による注意・指導があったとはいえない。」と判断されてしまい、会社が敗訴する可能性は高いといえます(仮に、退職前提の和解ができたとしても、高額の解決金を支払うことが要求されるでしょう。)。
5 冒頭の相談に対する回答
以上を前提に、冒頭の相談事例をみると、それまで問題行動に対し、「口頭注意」しか行ってこなかったとのことです。このため、会社が解雇を断行し、従業員が解雇無効の訴訟を提起した場合には、会社は、注意指導の事実を証明できず、その結果、敗訴する(=解雇無効)可能性が高いと予想します。
このため、冒頭の相談に対する回答としては、「この時点での解雇はリスクが高いので、やめた方がよい。」となります。
6 冒頭の相談に対するアドバイス
それでは、冒頭の相談事例では、どのように対応すればよいでしょうか。
まず、大前提として、このケースでは、ただちに解雇することはできないと考えてください。
そのうえで、「問題行動に対し、会社が注意指導したこと」を証拠化し(業務命令書や注意指導書の発行、懲戒処分など)、それを積み上げてもらいます。これらは、「会社が注意指導を繰り返しても改善しなかったこと」の証拠となります。
これらを繰り返しても、問題行動が改まらなかったときに、はじめて「解雇」を検討することになります(ただし、証拠が積み重なった時点でも、無用な訴訟に巻き込まれることを防ぐため、まずは「退職勧奨」するのがよいと考えます。)。
7 注意点
なお、上述した注意指導は、恣意的なものとならないようにしてください。例えば、他の従業員が同じミスをしても注意しないのに、その従業員のときだけ処分することは、会社側の対応が恣意的であり、問題があると言われてしまう危険があります。注意指導は公正・公平が大切です。
【関連ブログ】
退職勧奨を「パワハラ」と言われないようにするための注意点【会社向け】
違法な退職勧奨と言われないようにするための注意点【会社向け】
会社が解雇通告する前に検討すべきこと(解雇に潜むリスク)【会社向け】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
労災上乗せ保険加入のすすめ【会社向け】
会社が安全配慮義務を怠った結果、労災事故が発生した場合には、会社は被災者の損害を賠償しなければならないこととなります。今回は、そのような事態に備えて、労災上乗せ保険(使用者賠償責任保険など)に加入することの必要性について、ご説明します。
1 賠償額の高額化傾向
労災事故が発生した場合には、治療費のほか、休業損害、慰謝料、その他損害(通院交通費など)が損害として発生します。さらに、被災者に後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害に関する損害(逸失利益、後遺障害慰謝料)も損害賠償の対象となります。
特に、後遺障害に関する損害は、将来にわたる損害を補償する性質のものであることから、その損害額は高額となります。具体的には、後遺障害が認定されると、損害額は合計1000万円以上となり、高位の後遺障害が認定された場合には、賠償額が数千万円単位にのぼることもあります。
2 労災保険給付は損害の全部をカバーしないこと
以前にお話しましたとおり、労災保険給付は、被災者の損害の全部をカバーするわけではありません(労災事故における損害賠償リスク【会社向け】)。このため、「労災事故が起こっても、労災保険に加入しているから大丈夫だ。」ということにはなりません。上述しましたとおり、たとえ労災保険給付が支払われたとしても、会社は、1000万円以上(場合によっては、数千万円単位)の自己負担を余儀なくされる場合も十分に考えられるのです。
3 裁判となった場合の問題点
さらに、被災者から、損害賠償金の支払いを求めて訴えられた場合には、事態はさらに深刻となる可能性があります。すなわち、裁判で和解が不調となり、判決となった場合、会社は、上述した単位の賠償金を支払うよう命じられる危険があります。しかも、判決の場合、賠償金を一括して支払うよう命じられるのですが、これを支払うことができない場合には、強制執行を受けることになります。
そして、強制執行では、預金や売掛金を差し押さえられてしまうため、これらを別の支払いに充てることができません。さらに、預金や売掛金が差し押さえられた場合には、銀行からは借入金の一括返済を請求されるリスク、取引先からは信用不安を理由とする契約解除のリスクがあります。最悪の場合、会社は倒産する危険すらあります。
4 まとめ
以上のとおり、労災事故が発生した場合には、会社経営が非常に大きなダメージを受ける危険があります(実際に、労災事故の補償を余儀なくされた結果、資金繰り等の面で、深刻な影響を受けた会社は多数あります。)。このようなリスクを回避・軽減するためには、使用者賠償責任保険など、いわゆる労災上乗せ保険に加入することが有益です。
もし、加入していないのであれば、労災事故リスクの軽減を図るためにも、加入なさることを強くお勧めします(なお、保険の種類や補償内容については、保険会社にお問い合わせください。)。 このようなリスクに備えておくことも、「予防法務」の一環として、とても大切です。
【関連ブログ】
労災による損害賠償請求を受けた場合に、まず行うこと【会社向け】
労災による賠償請求があったときに検討すべきこと(被災者側の減額事由)【会社向け】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。