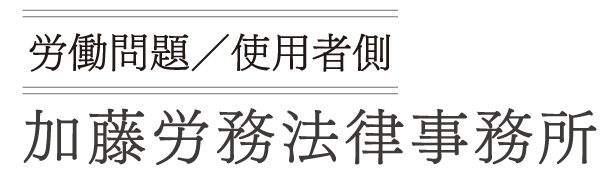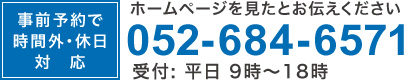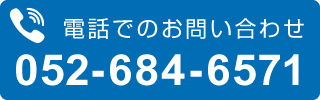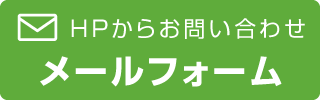「問題社員に辞めて欲しい」、「解雇しようと思っている」など、部下・従業員の解雇・退職問題にお困りの会社は多いと思います。そこで、今回は、「退職勧奨」についてご説明します。
1 退職勧奨とは
退職勧奨は、解雇ではありません。従業員の自発的な退職を促す行為です。従業員に「自発的に辞めてもらう」ことがポイントです。そこで、「自発的に辞めてもらう」ため、どのような働きかけを行うかが重要です。
2 問題がある退職勧奨の方法
退職勧奨で問題となる例としては、次のようなものがあります。
① 解雇事由がないにもかかわらず、「辞めないと解雇する」と言う。
② 連日、長時間にわたって執拗に退職を求める。
これらは、いずれも「従業員の自発的な退職を促す行為」とはいえません。「退職の強要」であり、裁判所で争われた場合、違法と判断される可能性が非常に高いといえます。
なお、違法と判断されると、「従業員の復職(職場復帰)」が認められるのみならず、会社は従業員に対する「復帰するまでの間の賃金」や「慰謝料」の支払義務が発生します。
3 退職勧奨する場合
「退職勧奨」といっても、部下・従業員に解雇事由があるか否かによって、対応方法が異なります。
① 解雇事由がある場合
この場合の退職勧奨は、部下・従業員のキャリアや退職金の支給等を考えて、自主退職を勧めるものです。
解雇事由が存在する以上、まずは退職勧奨を行い、本人がそれに応じなければ解雇権を行使することになります。
もっとも、「解雇事由があるか」について、会社と従業員との間で争いになることがあります。この点は、退職勧奨を行う前に、従業員の問題行動に関する証拠資料を集め、弁護士や社会保険労務士などの専門家と十分に協議してください。
証拠資料(書面など)がないにもかかわらず、「解雇事由がある」と主張しても、そのような主張が裁判所に認められる可能性は低いといわざるを得ません。この場合、「解雇事由があること」を前提に退職勧奨したとしても、後日、裁判所で争われた場合には、「解雇事由がある」という前提自体が崩れる危険があるので、ご注意ください。
② 解雇事由が存在しない場合
会社は、部下・従業員が退職勧奨に応じない場合には、解雇権を行使することはできません。
この場合には、会社が求める能力と本人の能力との間にミスマッチがあることについて、エピソードを交えながら説明する、退職勧奨に応じてもらうための条件提示(退職金の上乗せ等)を検討する等が重要です。「エピソードを交えながら説明する」というのは、例えば、メールや業務指導書などの資料を示しながら、具体的に説明することです。
「絶対に退職させよう」として、退職勧奨を執拗に繰り返すと、違法な退職勧奨と主張される危険があります。この場合には、いったん退職勧奨をやめて、部下・従業員の対応が改まったかを見守る必要があります。
4 まとめ
部下・従業員の退職勧奨を行う際の注意点を述べました。実際に退職勧奨を進めるには、会社の実情や対象となる部下・従業員の問題点など、それぞれの事案ごとで検討すべき事情が異なります。また、退職勧奨の話を持ち出すと、部下・従業員との信頼関係にもヒビが入ります。
退職勧奨は、「最後の手段」です。問題行動がある社員には、安易に退職勧奨を行うのではなく、それ以前に、根気強く注意・指導を繰り返す必要があります。このような対応は、後日、退職勧奨(あるいは、解雇)の効力が争われた場合、会社側に有利な事情として考慮されます。
これらを念頭に置いて、実際に退職勧奨を進める際には、慎重にご対応ください。
【関連ブログ】
退職勧奨を「パワハラ」と言われないようにするための注意点【会社向け】
違法な退職勧奨と言われないようにするための注意点【会社向け】
会社が解雇通告する前に検討すべきこと(解雇に潜むリスク)【会社向け】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。