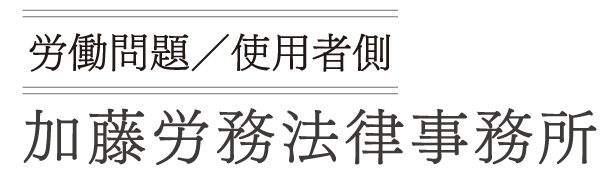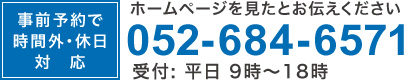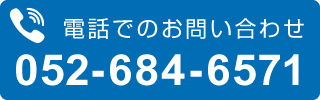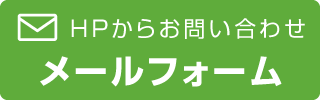労働審判は、原則として3回以内の期日で審理を終結することになっています。もっとも、ほとんどのケースでは、第1回期日の段階で、裁判所が具体的和解案を提示します。このため、労働審判は「第1回期日が勝負」です。したがって、従業員から労働審判を申し立てられた場合、会社は、直ちに対応準備に取り掛からないといけません。
今回は、労働審判を申し立てられた場合の会社の初動対応について、ご説明します。
このページの目次
事実関係の整理(時系列にまとめる。)
労働審判を申し立てられた場合、会社だけで対応することは事実上不可能です。弁護士に依頼して、会社の言い分を裁判所にきちんと伝える必要があります。そして、そのためには、まずは弁護士に、事実関係を正確に伝えなければなりません。
これまでの経験上、弁護士に事実関係を正確に伝えるためには、次の点に注意していただくのがよいと思います。
まずは、労働審判申立書を読んでください。そして、従業員が何を要求しているかを確認してください。また、労働審判申立書には、申立てに至る事実経緯が記載されています。これに対し、会社側の言い分を時系列に沿って作成してください(簡単なもので構いません。)。
事件の類型によって、重要となる証拠・ポイントは、次のとおりです。
① 退職が争われるケース(不当解雇)
退職時に本人が提出した書面があるかを確認するとともに(退職届など)、関係者(上司、同僚など)から退職に至る経緯を聴取してください。なお、退職に至る過程でメールのやりとりをしている場合も多いので、メールも確認してください。
② パワハラが争われるケース
通常であれば、労働審判を申し立てられる前に、従業員(申立人)からパワハラ被害に関する申告があったはずです。そのときの調査結果を確認するとともに、労働審判申立書に記載された内容を踏まえ、再度、関係者に聴取してください。
③ 残業代請求の場合
労働時間に関する資料(勤怠記録など)を確認するとともに、給与計算の内容について社会保険労務士(社労士)に確認してください(給与計算を社労士に依頼している場合)。
なお、早い時点で弁護士に委任することができた場合には、関係者への聴取の際、弁護士にも同席してもらいましょう。そうすることで、準備と時間が節約できます。
速やかに弁護士へ相談・依頼すること
労働審判申立書に対する反論書の提出期限は、日程がタイトです。そこで、上記の調査と並行して、弁護士に相談し、速やかに依頼してください。
労働審判は裁判に準じた手続であり、専門的な知識・経験がないと対応できません。「自社で何とかなるだろう。」と考えてはいけません。
依頼する弁護士が見つかった場合には、早急に弁護士と打合せを行ってください。このとき、事実関係を時系列に沿って整理していると、弁護士もスピーディーに事案を理解することができます。また、労働審判では、会社側の証人として関係者(上司や同僚など)が同行し、裁判所に事実関係を説明する必要があります。会社側証人を決めるためにも、弁護士との打合せはただちに実施する必要があります。
最後に
労働審判を申し立てられた場合の初動対応についてご説明しました。この手続は、「第1回期日が勝負」です(第1回期日で裁判所から和解案が提示されるケースが大半です。)。そこで、裁判所から労働審判申立書が届いたら、速やかに対応することが重要です。
加藤労務法律事務所は、これまで会社側代理人として多数の労働審判事件を取り扱っており(解雇事件・内定取消事件など)、ポイントを押さえた準備・書面作成・期日対応を行います。労働審判を申し立てられた企業様は、加藤労務法律事務所へご相談ください。
→ お問い合わせは、こちらまで(お問い合わせ画面に移動します)
【関連ブログ】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。