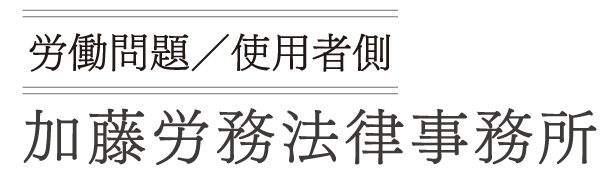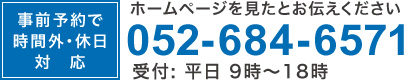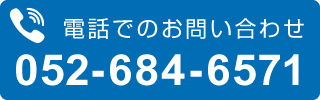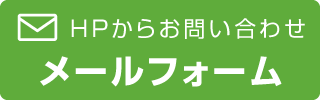Posts Tagged ‘労災’
労災による賠償請求があったときに検討すべきこと(被災者側の減額事由)【会社向け】
過重労働が原因で脳出血や心筋梗塞などの疾病が発症したとします。この場合、会社は被災者に対し、安全配慮義務違反による損害賠償義務を負うこととなります。しかし、被災者が高血圧であった、あるいは、飲酒・喫煙習慣があった等、疾病の原因となる基礎疾患や生活習慣を有していた場合、これらの点は、どのように取り扱うことになるでしょうか。今回は、被災者側の減額事由について、ご説明します。
1 被災者側の減額事由
被災者が過重労働等の業務に起因して脳出血や心筋梗塞などの疾病を発症した。他方で、その被災者には、高血圧の治療歴や飲酒・喫煙の生活習慣があった。
この場合、被災者が疾病を発症したのは、過重労働(会社の安全配慮義務違反)と既往症・生活習慣(被災者側の事情)が競合した結果と考えることができます。仮に、被災者側にこれらの事情がある場合には、疾病を原因とする被災者の損害について、その全てを会社に負担させることは当事者間の公平に欠ける結果となりかねません。つまり、被災者側に基礎疾患や生活習慣がなければ、ここまで損害が大きくならなかったといえる場合には、損害の全部について、会社に賠償責任を負わせるのが正しいか、ということです。
労災による損害賠償が争われる場合には、このような観点から、会社の被災者に対する損害賠償責任について、一定割合の減額がされる場合があります。
例えば、長時間労働によって疾病が発症したケースにおいて、被災者の生活習慣(飲酒・喫煙習慣)、持病の治療を受けていなかった点を踏まえ、会社側が負担すべき損害額が減額された事案も存在します。
2 実務上の注意点
以上が原則です。
ところが、実務では、被災者側の事情を「立証」(証明)しなければならないというハードルが存在します。つまり、抽象的に、「飲酒習慣があった。」、「喫煙習慣があった。」、「高血圧であった。」等と言うだけでは、裁判所は取り上げてくれません。
したがって、これらの事情をいかにして立証するかが重要となりますが,実は,この立証問題が難しいのです。
過去に取り扱ったケースでは、被災者本人のカルテを取り付けたところ、本人自筆の問診票に基礎疾患に関する記載(高血圧の治療歴)や生活習慣に関する記載(ヘビースモーカーであったこと)があったため、これらを証拠提出したところ、減額事由となる被害者側の事情が認定され、一定割合の減額が認められたことがあります。
3 まとめ
先般、高年齢者雇用安定法が改正されたことに伴い、今後、高齢労働者が就労する機会は、さらに増えていくでしょう。年齢を重ねるほど、高血圧などの基礎疾患を抱える人は増え、脳出血などの発症リスクは高まると考えられます。そして、脳出血等の疾病が発症した場合、労災であると主張されるリスクは高いと予想します。
このような主張を防止するためには、まずは長時間労働を抑制することが重要です。さらに、賠償額の適正化という観点から、労働者の健康管理の重要性は、ますます高くなると考えます。
【関連ブログ】
労災による損害賠償請求を受けた場合に、まず行うこと【会社向け】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
労災による損害賠償請求を受けた場合に、まず行うこと【会社向け】
労災事故が発生し、被災者(従業員)が労災認定された。この場合、会社は、被災者から安全配慮義務に違反したとして、損害賠償請求を受けることがあります。今回は、そのような請求を受けた場合に、まずは会社が行うべきことについて、ご説明します。
1 労災事故を理由とする損害賠償請求
労災事故が発生し、被災者が労災認定された。この場合、会社は、被災者から、労災保険給付では補償されなかった損害について、多額の損害賠償請求を受けることがあります。
この場合、どのように対応すればよいでしょうか。
2 まずは、弁護士に相談すること
被災者(実際は、その代理人弁護士)から損害賠償請求の書類が届いたら、まずは弁護士に相談してください。その際、労基署に提出した労働者死傷病報告や労災申請の関係で提出した書類の控えがあれば、それを持参してください。また、社内で労災事故を調査していれば、それらの資料も持参してください。
これらの資料があれば、相談を受けた弁護士は、事故状況、被災者の怪我の程度など、事案の概要を把握できます。例えば、後遺障害が残存したとして、逸失利益や後遺障害慰謝料の請求があった場合、認定された後遺障害の内容・程度によって、これらの損害(逸失利益・後遺障害慰謝料)の概算額を計算して、請求額の妥当性を検証することが可能となります。
3 事故状況の把握
事故状況は、被災者にも過失があったといえるかを検討する材料となります。例えば、被災者が構内ルールを守らなかった結果、事故に遭ったのであれば、被災者の過失を問える可能性があります。この場合、過失相殺の主張(被災者の過失分は自己負担すべきとの主張)が可能となります。
仮に、過失相殺の主張ができるのであれば、これにより、賠償額の圧縮を図ることが可能です。例えば、被災者の過失割合が20%の場合、総損害の20%を控除できることになります(総損害が1000万円の場合、そこから200万円を控除できることになります。)。
被災者は、過失相殺をしないで損害賠償請求することが多数あります。しかし、実際は、過失相殺できる場合もありますので、事故状況に関する資料は非常に重要です。
4 怪我の程度の確認
被災者の怪我の程度(特に、事故当初の怪我)の程度を確認することも重要です。例えば、軽傷事案(打撲など)であるにもかかわらず、休業期間が長期化していた場合、被災者が請求する休業損害は過大であり、その全てを賠償する必要はないと主張できる可能性があります。また、怪我と比べて休業期間が長いと思われる場合には、労災事故による怪我だけでなく、別の要因も相まって長期化したのではないかと考えることもできます。
後遺障害が残存した場合には、当初の怪我と認定された後遺障害との間に整合性があるかも重要なポイントです。労災事故による怪我と既往症(事故前からの持病など)が相まって後遺障害が残った場合には、後遺障害に関する損害(逸失利益、後遺障害慰謝料)について、一定割合の減額主張が可能となる場合もあります。この点については、過去の裁判例を参考に、① 減額できるか否か、② 減額できるとして、どれくらい減額できるか、を検討することになります。
これらについては、「労災に関する知識」のみならず、「損害賠償の裁判実務に関する知識・経験」が必要な分野です。
5 まとめ
今回は、会社が被災者から損害賠償請求を受けた場合に、まずは行うべきことをご説明しました。 多額の損害賠償請求の書類を受け取ると、驚きのあまり、何をすればよいか分からず、途方に暮れるかもしれません。でも、皆さんの会社の味方となってくれる人は必ずいます。今回のブログを参考に、やるべきことを一つずつ実行してください。
【関連ブログ】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
労災事故における労働者の過失(過失相殺)【会社向け】
労災事故の対応でお困りの企業様は、加藤労務法律事務所までご相談ください。
→ お問い合わせは、こちらまで(お問い合わせ画面に移動します)
加藤労務法律事務所の紹介ページ
労災事故が発生した場合、会社が事故防止措置を講じていなければ、会社は被災した労働者に対し、損害賠償義務を負うこととなります(事故防止措置が不十分であった場合も含む。)。
それでは、事故の原因が労働者側にもあった場合、労働者の全ての損害について、会社は賠償責任を負うことになるのでしょうか。今回は、労災事故における労働者の過失(過失相殺)についてご説明します。
1 過失相殺
例えば、構内事故で被災者が安全具を付けていなかった結果、労災事故に遭った場合、その事故は、会社の責任(安全教育の不徹底)と労働者の責任(安全具の不着用)が競合した結果、発生したことになります。この場合、労災事故によって発生した労働者の損害について、その責任の全てが会社にあるとはいえません。他方で、その責任の全てが被災した労働者側にあるともいえません。
このように、労災事故の原因が会社と労働者の双方にあるといえる場合には、その責任を会社と労働者の双方に案分することになります。これを、「過失相殺」といいます。例えば、事故状況から、労働者の過失が30パーセントと認められる場合には、その損害のうち30パーセント分については、会社の請求できないこととなります。つまり、会社は、労働者の過失分については損害賠償義務を免れることとなるのです。
2 過失割合の算定方法
それでは、過失割合は、どのように算定されるのでしょうか。この点については、決まった数式等が存在するわけではありません。すなわち、過失割合は、事故状況、事故原因、会社側の義務違反の内容、労働者の不注意の内容等を総合して判断されることになります。
非常に曖昧かつ抽象的な表現となってしまいますが、損害賠償の実務では、労災事故が発生した場合には、これらの事情を精査して、労働者と協議して、過失割合を決定(合意)することになります(なお、労災事故の場合には、事案にもよりますが、労働者側の過失割合は20~30パーセントとなるケースが多いというのが私の個人的感覚です。)。
3 まとめ
損害額の計算は、実務上、確立された計算式があります。これに対し、過失割合については、そのような計算式がありません。そこで、過失割合は、労働者と協議して決めることとなります。
この場合、会社は、労働者に対し、説得力のある提案を行う必要がありますが、そのためには、事故状況、事故原因、会社側の義務違反の内容、労働者の不注意の内容等を精査する必要があります。
そして、これらの情報に基づいて、労働者の過失割合を検討することになるところ、何パーセントが妥当であるかは、過去の裁判例などを参考に決める必要があります。
過失割合の検討については、裁判例の分析・検討が必要となるため、弁護士などの専門家に相談するのがよいといえます。
労災事故の対応でお困りの企業様は、加藤労務法律事務所までご相談ください。
→ お問い合わせは、こちらまで(お問い合わせ画面に移動します)
加藤労務法律事務所の紹介ページ
【関連ブログ】
労災による損害賠償請求を受けた場合に、まず行うこと【会社向け】
労災による賠償請求があったときに検討すべきこと(被災者側の減額事由)【会社向け】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。