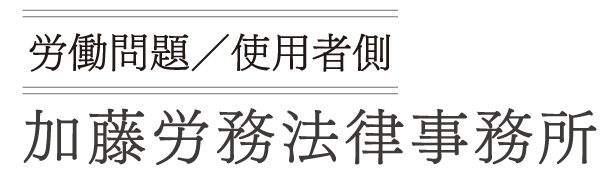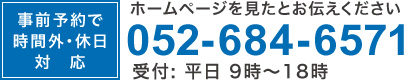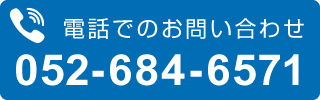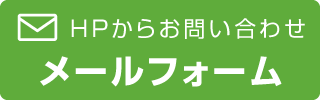今回は、企業の労務担当の皆様に向けて、「休職発令時に注意すべき点」について、Q&A形式で解説いたします。
このページの目次
■ 休職とは?~まずは基本的な位置づけを理解しましょう~
休職とは、従業員が業務に従事することが困難な事情が生じた場合に、一定期間、労働義務を免除し、従業員の身分を維持したまま就労を停止させる制度です。「業務に従事することができない」=「労働者の債務不履行」であり、解雇事由となります。休職は、一定期間、労働義務を免除するものであり、その間、会社は従業員を解雇できないこととなります。したがって、休職とは「解雇猶予措置」と考えられています。
休職は、就業規則等で定めることによって初めて認められる制度であり、労働基準法や労働契約法といった法律上の制度ではありません。法律上の義務ではないものの、ほとんどの企業で就業規則上に規定されているのが実情です。
<休職理由の典型例>
- 病気・ケガ
- メンタルヘルス不調(うつ病・適応障害等)
- 長期入院が必要な疾患
<休職の法的性質>
休職は、「解雇の猶予措置」と考えられています。
すなわち、業務遂行が困難であるにもかかわらず、すぐに解雇するのではなく、一定期間回復を待ち、その間は労働契約を維持するという措置です。
このため、休職の運用には慎重な判断(就業規則の該当性判断)と適切な情報収集が不可欠です。
■ Q&A:休職発令時の実務的な注意点とは?
以下では、労務担当の皆様が実際に休職を発令する際に直面する疑問にお答えいたします。
Q1. 休職を発令するには、どのような基準で判断すべきですか?
A1. 就業規則に定める「休職事由」に該当するかどうかを判断することになります。
就業規則は、各社によって内容が異なります(例:私傷病により引き続き30日以上勤務できないと会社が認めたとき)。
なお、就業規則に該当するか否かを判断するにあたっては、「欠勤を開始した時点の診断書」と「休職発令時の診断書」の内容(傷病名、症状、治療見込み期間など)を慎重に確認する必要があります。
Q2. 休職中にやってはいけない対応はありますか?
A2. 復職の可能性を検討せずに形式的に休職期間を消化させるだけの対応はリスクがあります。
企業には、従業員の回復状況を適切に把握し、休職期間満了時に「復職可能かどうか」を判断する必要があります。このプロセスを怠ると、復職に関する会社側の判断が不十分であるとして、会社が不利益を被るリスクがあります(例:休職期間満了による解雇・退職が無効と判断される等)。
したがって、休職期間中、定期的に休職者と連絡をとり、その病状、治療期間の見込み、復職の可否を確認しておく必要があります。
Q3. 休職中、復職可否の情報はどのように収集すればよいですか?
A3. 医師の意見聴取や、本人へのヒアリングが基本です。必要に応じて産業医の意見も活用します。
以下のような情報収集を行うのが適切です。
- 主治医の診断書の取得(定期的な提出を求める。)
- 回復見込みの有無・時期の見通しにつき、主治医・本人の意見を聞く。
- 本人の意思確認とヒアリング
- 産業医からの意見聴取、本人と産業医との面談
主治医の診断書のみに依存せず、企業側として復職の可否を判断する材料を主体的に集める姿勢が求められます。また、主治医に意見を聞く場合には、本人の同意書が必要となります。これについては、休職発令時に本人から取り付けておくのがよいでしょう。
Q4. 主治医の診断書が「復職可」となっていれば、必ず復職させる必要がありますか?
A4. 必ずしもそうではありません。企業が復職の可否を判断する必要があります。
主治医の診断書はあくまで「医学的見地」からの意見であり、最終的な判断は企業に委ねられています。また、主治医は、本人の業務内容を十分に理解しておらず、一般論として「復職可」としている場合も多いので、注意が必要です。主治医の診断書に疑問がある場合には、主治医に面談をお願いすることも検討してください(この場合、本人の同意書が必要となります。)。
復職の可否は、会社が判断することになります。この場合、復職後の業務遂行能力、職場環境との適合性、再発の可能性などを総合して、休職期間満了時において、再び労務を提供することが可能であるかを判断することになります。
復職可否を判断するにあたっては、産業医の意見や、試し出勤の活用も有効です。
Q5. 情報収集の際、プライバシー保護はどのように配慮すべきですか?
A5. 医療情報や私生活に関する情報の収集は、本人の同意が必要となります。
医療情報や私生活に関する内容は、個人情報保護の観点からも慎重に取り扱う必要があります。
情報収集にあたっては、以下の点に注意してください。
- 情報取得の目的を明確にし、本人に説明
- 書面または記録に残る形で同意を取得
- 最小限の必要情報のみ収集
- 情報は関係者以外に開示しない
Q6. 休職期間満了後、復職できない場合にはどうすればよいですか?
A6. 就業規則に基づき「自然退職」とするケースや、「解雇」を検討する場合もありますが、いずれも慎重な対応が必要です。
休職期間が満了しても就労が不可能な場合、以下の選択肢があります。
- 自然退職(当然退職)
- 就業規則で「休職期間満了時に復職できない場合は自然退職」と規定されている場合に限られます。
- 復職可能性について十分な調査・検討が必要です。「程なくして復職可能」(2、3か月程度で復職可能)である場合に「復職不可能」として退職扱いとすることは、後日、「退職扱いは無効」と判断される可能性があります。
- 解雇
- 就業規則で「休職期間満了時に復職できない場合は解雇」と規定されている場合は、解雇手続をとる必要があります。
- 復職可能性について十分な調査・検討が必要であるほか、解雇手続に従った措置が必要となります(例:解雇予告手当を支給する必要があること、解雇の意思表示を本人に伝える必要があること等)。
いずれの場合も、復職可能性の有無についての十分な情報収集と、本人との面談記録、医師の意見等といった証拠を整えておく必要があります。
Q7. 復職後に再度欠勤するようになった場合、どう対応すべきですか?
A7. このような場合に備えて、就業規則に通算規定の導入を検討しましょう。
復職後の短期間で再度の休職となった場合に備えて、復職後、一定期間に同じ傷病で欠勤した場合には休職期間に通算する旨の規定の導入を検討してください。
■ まとめ:休職制度の運用は「ゴールを見据えた対応」が重要です
休職は、「解雇猶予」を目的とした制度です。このような制度目的に沿った対応が必要となります。休職期間満了時に復職できない場合、従業員は解雇・退職となります。このため、休職発令時の段階から、「休職期間満了時の復職の可否」を検討しなければならないことを意識する必要があります。
具体的には、休職発令時の段階から、以下の点に注意して、休職制度を運用するよう心がけてください。
- 就業規則に規定された要件の確認
- 復職可否に関する客観的情報の収集(医師・産業医・本人)
- 情報収集におけるプライバシーへの配慮(同意書の取得)
- 本人との定期的な連絡(病状、治療状況など)
- 主治医との情報共有(本人の病状、会社での仕事内容など)
【関連ブログ】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。