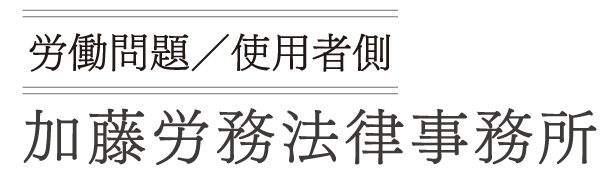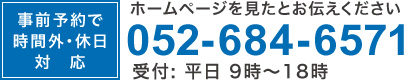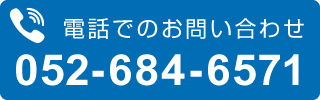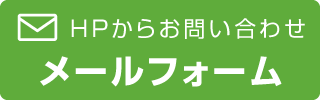定年後再雇用(継続雇用)の労働条件は、会社が自由に決めることができるのでしょうか?
今回は、従業員を定年後再雇用する場合に、どのような労働条件を設定することができるかについて、ご説明します。
このページの目次
労働条件の提示に関する原則
定年後再雇用は、定年後の新たな労働契約の締結となります。契約は、当事者の合意によって成立するため、どのような労働条件で採用するかにつき、必ずしも労働者の希望に沿う必要はありません。
この点について、厚生労働省のホームページにある「高年齢者雇用安定法Q&A」にも、「高年法が求めているのは、継続雇用制度の導入であり、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではな」いと記載されています(高年齢者雇用安定法Q&AのQ1-9)。
もっとも、労働条件の提示が全くの自由かというと、そうではありません。定年後再雇用(継続雇用)は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年法)に基づく雇用確保措置の一つです。このため、定年後再雇用の労働条件は、会社が自由に設定できるわけではなく、高年法の趣旨を尊重しなければなりません。
高年齢者雇用安定法Q&A(Q1-9)は、「事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年法違反となるものではない。」としています。これを反対解釈すると、高年法は、事業主に対し、合理的な裁量の範囲内での労働条件の提示を要求しているといえます。
それでは、「合理的な裁量の範囲内」とは、どのようなものでしょうか?
この点について参考となる裁判例として、「トヨタ自動車事件」(名古屋高裁平成28.9.28)と「九州惣菜事件」(福岡高裁平成29.9.7)があります。
トヨタ自動車事件(名古屋高裁平成28.9.28)
事務職に従事してきた従業員に対し、定年後再雇用の職種として清掃業務を提示したことを違法と判断した裁判例です。違法と判断した理由は、次のとおりです。
① 定年後の継続雇用として、どのような労働条件を提示するかについては、会社に一定の裁量がある。ただし、提示した労働条件が、到底容認できないような低額の給与水準であること、社会通念に照らし当該労働者にとって到底受け入れがたい職務内容など、実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない場合には、高年法の趣旨に反して違法となる。
② 会社が提示した業務内容は、それまでの職種に属するものとは全く異なった単純労務職としてのものであり、原告がいかなる事務職の業務についてもそれに耐えられないなど通常解雇に相当するような事情が認めれない限り、違法である。
この裁判例は、従業員を定年後再雇用(継続雇用)する際、その職務内容にも配慮しなければならないことを示唆する内容です。
もっとも、「(被告は)我が国有数の巨大企業であって事務職としての業務には多種多様なものがあると考えられるにもかかわらず、(中略)清掃業務等以外に提示できる事務職としての業務があるか否かについて十分な検討を行ったとは認め難い。」と判示しており、裁判所が違法と判断したのは、被告となった会社の企業規模も相当程度影響していたものと考えられます。
九州惣菜事件(福岡高裁平成29.9.7)
定年後再雇用者を時給制のパートタイム勤務とすることで、定年前と比較して大幅な賃金引下げを伴う労働条件の提示(定年前の25%)が違法と判断されました。違法と判断した理由は、次のとおりです。
① 労働者である高年齢者の希望・期待に著しく反し、到底受け入れ難いような労働条件を提示する行為は不法行為となり得る。継続雇用制度は、定年前後における労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることを原則とすべきであり、例外的に継続性・連続性が欠ける労働条件の提示が許容されるためには、合理的な理由が必要である。
② 原告の賃金を月収ベースで比較すると、定年前の約25%に過ぎない。このような大幅な賃金の減少を正当化する合理的な理由が必要であるが、正当化する合理的理由は存在しない。
合理的な裁量を逸脱する場合とは?
これらの裁判例をみると、合理的な裁量の範囲を逸脱する場合として、①著しく低額な賃金を提示する場合、②職務内容の大幅な変更を伴う場合が考えられます。
もっとも、「職務内容の大幅な変更」については、企業規模や人員構成によっては必ずしも合理的な裁量を逸脱したとはいえない場合もあり得ると考えます。具体的には、企業規模・人員構成、業務の属人化防止、スタッフの若返り等の理由から、定年後再雇用に伴って職種を大きく変更することにつき、やむを得ない理由がある場合には、合理性が認められる可能性もあると思います。
定年後再雇用時に従業員の職務内容の変更を希望する場合には、定年前から適性に関する資料・証拠を集めておくとともに(「従前の職務に従事させることが相当ではないこと」の証拠)、定年前の人事考課の結果、会社規模、対象業務の人員状況等を踏まえ、対象者と十分に協議し、了承が得られるよう努めることが必要となります。
「賃金の低下」に関し、「定年前の賃金の○%以下であれば違法」という明確な基準はありません。
提示額が合理的な裁量の範囲内であるかは、提示する労働条件(労働日、労働時間、業務内容、業務の難易等)を踏まえ、個別具体的に判断することになります。職務内容を変更するとともに、これに伴って労働日・労働時間を減らす場合には、賃金の減額提示も合理性があると考えられます。もっとも、九州惣菜事件が「25%は違法」と判断したことを踏まえますと、最低ラインとして、25%を下回らないよう配慮するのがよいでしょう。

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。