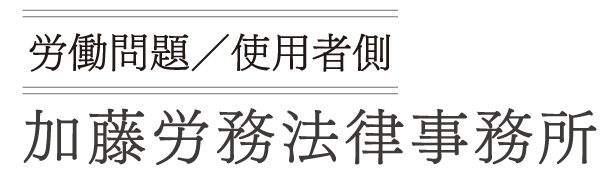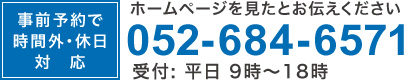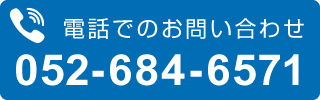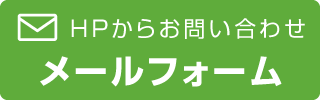Archive for the ‘ブログ(業務にお役立てください。)’ Category
休職発令時の注意点
今回は、企業の労務担当の皆様に向けて、「休職発令時に注意すべき点」について、Q&A形式で解説いたします。
■ 休職とは?~まずは基本的な位置づけを理解しましょう~
休職とは、従業員が業務に従事することが困難な事情が生じた場合に、一定期間、労働義務を免除し、従業員の身分を維持したまま就労を停止させる制度です。「業務に従事することができない」=「労働者の債務不履行」であり、解雇事由となります。休職は、一定期間、労働義務を免除するものであり、その間、会社は従業員を解雇できないこととなります。したがって、休職とは「解雇猶予措置」と考えられています。
休職は、就業規則等で定めることによって初めて認められる制度であり、労働基準法や労働契約法といった法律上の制度ではありません。法律上の義務ではないものの、ほとんどの企業で就業規則上に規定されているのが実情です。
<休職理由の典型例>
- 病気・ケガ
- メンタルヘルス不調(うつ病・適応障害等)
- 長期入院が必要な疾患
<休職の法的性質>
休職は、「解雇の猶予措置」と考えられています。
すなわち、業務遂行が困難であるにもかかわらず、すぐに解雇するのではなく、一定期間回復を待ち、その間は労働契約を維持するという措置です。
このため、休職の運用には慎重な判断(就業規則の該当性判断)と適切な情報収集が不可欠です。
■ Q&A:休職発令時の実務的な注意点とは?
以下では、労務担当の皆様が実際に休職を発令する際に直面する疑問にお答えいたします。
Q1. 休職を発令するには、どのような基準で判断すべきですか?
A1. 就業規則に定める「休職事由」に該当するかどうかを判断することになります。
就業規則は、各社によって内容が異なります(例:私傷病により引き続き30日以上勤務できないと会社が認めたとき)。
なお、就業規則に該当するか否かを判断するにあたっては、「欠勤を開始した時点の診断書」と「休職発令時の診断書」の内容(傷病名、症状、治療見込み期間など)を慎重に確認する必要があります。
Q2. 休職中にやってはいけない対応はありますか?
A2. 復職の可能性を検討せずに形式的に休職期間を消化させるだけの対応はリスクがあります。
企業には、従業員の回復状況を適切に把握し、休職期間満了時に「復職可能かどうか」を判断する必要があります。このプロセスを怠ると、復職に関する会社側の判断が不十分であるとして、会社が不利益を被るリスクがあります(例:休職期間満了による解雇・退職が無効と判断される等)。
したがって、休職期間中、定期的に休職者と連絡をとり、その病状、治療期間の見込み、復職の可否を確認しておく必要があります。
Q3. 休職中、復職可否の情報はどのように収集すればよいですか?
A3. 医師の意見聴取や、本人へのヒアリングが基本です。必要に応じて産業医の意見も活用します。
以下のような情報収集を行うのが適切です。
- 主治医の診断書の取得(定期的な提出を求める。)
- 回復見込みの有無・時期の見通しにつき、主治医・本人の意見を聞く。
- 本人の意思確認とヒアリング
- 産業医からの意見聴取、本人と産業医との面談
主治医の診断書のみに依存せず、企業側として復職の可否を判断する材料を主体的に集める姿勢が求められます。また、主治医に意見を聞く場合には、本人の同意書が必要となります。これについては、休職発令時に本人から取り付けておくのがよいでしょう。
Q4. 主治医の診断書が「復職可」となっていれば、必ず復職させる必要がありますか?
A4. 必ずしもそうではありません。企業が復職の可否を判断する必要があります。
主治医の診断書はあくまで「医学的見地」からの意見であり、最終的な判断は企業に委ねられています。また、主治医は、本人の業務内容を十分に理解しておらず、一般論として「復職可」としている場合も多いので、注意が必要です。主治医の診断書に疑問がある場合には、主治医に面談をお願いすることも検討してください(この場合、本人の同意書が必要となります。)。
復職の可否は、会社が判断することになります。この場合、復職後の業務遂行能力、職場環境との適合性、再発の可能性などを総合して、休職期間満了時において、再び労務を提供することが可能であるかを判断することになります。
復職可否を判断するにあたっては、産業医の意見や、試し出勤の活用も有効です。
Q5. 情報収集の際、プライバシー保護はどのように配慮すべきですか?
A5. 医療情報や私生活に関する情報の収集は、本人の同意が必要となります。
医療情報や私生活に関する内容は、個人情報保護の観点からも慎重に取り扱う必要があります。
情報収集にあたっては、以下の点に注意してください。
- 情報取得の目的を明確にし、本人に説明
- 書面または記録に残る形で同意を取得
- 最小限の必要情報のみ収集
- 情報は関係者以外に開示しない
Q6. 休職期間満了後、復職できない場合にはどうすればよいですか?
A6. 就業規則に基づき「自然退職」とするケースや、「解雇」を検討する場合もありますが、いずれも慎重な対応が必要です。
休職期間が満了しても就労が不可能な場合、以下の選択肢があります。
- 自然退職(当然退職)
- 就業規則で「休職期間満了時に復職できない場合は自然退職」と規定されている場合に限られます。
- 復職可能性について十分な調査・検討が必要です。「程なくして復職可能」(2、3か月程度で復職可能)である場合に「復職不可能」として退職扱いとすることは、後日、「退職扱いは無効」と判断される可能性があります。
- 解雇
- 就業規則で「休職期間満了時に復職できない場合は解雇」と規定されている場合は、解雇手続をとる必要があります。
- 復職可能性について十分な調査・検討が必要であるほか、解雇手続に従った措置が必要となります(例:解雇予告手当を支給する必要があること、解雇の意思表示を本人に伝える必要があること等)。
いずれの場合も、復職可能性の有無についての十分な情報収集と、本人との面談記録、医師の意見等といった証拠を整えておく必要があります。
Q7. 復職後に再度欠勤するようになった場合、どう対応すべきですか?
A7. このような場合に備えて、就業規則に通算規定の導入を検討しましょう。
復職後の短期間で再度の休職となった場合に備えて、復職後、一定期間に同じ傷病で欠勤した場合には休職期間に通算する旨の規定の導入を検討してください。
■ まとめ:休職制度の運用は「ゴールを見据えた対応」が重要です
休職は、「解雇猶予」を目的とした制度です。このような制度目的に沿った対応が必要となります。休職期間満了時に復職できない場合、従業員は解雇・退職となります。このため、休職発令時の段階から、「休職期間満了時の復職の可否」を検討しなければならないことを意識する必要があります。
具体的には、休職発令時の段階から、以下の点に注意して、休職制度を運用するよう心がけてください。
- 就業規則に規定された要件の確認
- 復職可否に関する客観的情報の収集(医師・産業医・本人)
- 情報収集におけるプライバシーへの配慮(同意書の取得)
- 本人との定期的な連絡(病状、治療状況など)
- 主治医との情報共有(本人の病状、会社での仕事内容など)
【関連ブログ】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
操作ミスによる労災事故の裁判例(従業員の過失20%)
事案の概要
従業員が、工場で働いている際にプレス機に指を挟まれて負傷したとして、1731万2894円を請求した事案(タイミングを誤って、右手を離す前にフットスイッチを踏んだ結果、右手の中指がプレス機に挟まれた。)。
結論
会社は、従業員に対し、1029万2894円を支払う旨の判決となりました。
理由
1 安全配慮義務違反
① 会社は、労働安全衛生規則28条及び131条に基づき、使用していたプレス機に安全装置を取り付ける措置を講じるとともに、安全装置が有効な状態で使用されるよう点検及び整備を行う義務を負う。また、労働安全衛生法14条、同法施行令6条7号、労働安全衛生規則134条3号に基づき、作業主任者を選任した上で、当該作業主任者に安全装置の切替キースイッチの鍵を保管させる義務を負う。これらの義務は、労働者の身体の安全を確保することを目的とするものであるから、当該義務に違反した場合には安全配慮義務にも違反したものというべきである。
本件では、プレス機には安全装置が取り付けられていたが、本件事故当時、何者かが安全装置の電源を切ったことにより、本件事故が発生したと推認できる。このような事故の態様や安全装置の切替キースイッチの鍵を保管者ではない使用者が使用できる状態であったことに鑑みると、会社は、作業主任者に安全装置の鍵を保管させる義務に違反したというべきである。
なお、会社は、被害者である従業員が安全装置の電源を切ったと主張しましたが、同主張は裁判所に採用されませんでした。
② 会社は、労働安全衛生法35条1項に基づき、プレス機を操作する従業員に対し、その雇い入れ又は作業内容変更の際に、取り扱う機械の危険性及び取扱方法、具体的な作業手順、作業開始前の点検等に関する安全衛生教育を行う義務を負っており、これに違反した場合には、安全配慮義務に違反したものというべきである。
被害者(ベトナム人)は、会社で先に働いていたベトナム人の従業員がプレス機の操作を5分程度実演する方法によりプレス機の操作方法を学んで操作するようになり、分からない点があれば、当該従業員に教えてもらいながら作業していた。他方で、プレス機のセッティング等の作業は他の従業員が行っており、被害者にはその知識がなかった。この指導方法や時間に照らせば、プレス機の危険性及び取扱方法について被害者が十分な説明を受けていたとは評価できない。また、会社において、被害者が理解できるベトナム語を使用した教材を活用した教育は実施されていなかったと推認できる。よって、会社は、被害者に対して安全衛生教育を行う義務に違反していたものというべきである。
2 過失相殺
被害者は、遅くとも平成26年5月頃から本件事故(平成27年1月28日)までの間にほぼ毎日のようにプレス機を操作し、フットスイッチを踏めばプレス機が作動し、その際にプレス機に手を入れたらプレス機に挟まれることを認識していた。このように、被害者は、本件事故までにプレス機の操作経験を少なくとも8か月間有しており、プレス機の作動範囲に手を入れることの危険性を認識していたにもかかわらず、不注意により本件事故を発生させており、本件事故につき一定の過失があったといわざるを得ない。そして、会社の安全配慮義務の内容や、指導の方法や時間に照らし、プレス機の操作について被害者が十分な説明を受けていたとは評価できないこと、被害者が作業を急いでいた原因が会社側の指示によるものであったこと等を考慮すると、原告の損害につき、2割の過失相殺をするのが相当である。
3 その他(後遺障害逸失利益)
判決では、被害者の後遺障害等級を12級9号に該当すると判断している。その上で、その労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を33年(症状固定時34歳)と判示した。
基礎収入に関し、被害者が日本語をほとんど理解できないことを踏まえ、平均賃金相当額(402万円)を取得する蓋然性があるとは認められないと判断している。そして、比較的若年であること、現在、約22万円の月収を得ていることから、逸失利益算定における基礎収入としては、年収300万円(上記平均賃金の75%)蔓延と認めるのが相当であると判示した。
コメント
本裁判例(大阪地判令和6年7月31日)は、従業員の操作ミスによる労災事故に分類することができます。判決では、安全装置の鍵に関する保管に問題があったこと、安全教育が十分に行われたとはいえないことから、会社に安全配慮義務違反を認めています。安全装置を設置するのみならず、その後の運用や安全衛生教育にも注意を払う必要があることを示唆する裁判例といえます。
労災事故の裁判(示談)では、労働者側から、安全衛生教育を行う義務に違反していたと主張されることが多いですが、本裁判例も、会社が安全衛生教育を実施したか否かを重視しています。したがって、会社は、従業員に対し、機械の使用方法について、しっかりと安全衛生教育を行う必要があります。
本件のような操作ミス型の労災事故では、過失相殺は20~40%の範囲で行われることが多いと思われますが、本件も、その範囲内で過失相殺しています。

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
経歴詐称(過去の犯罪歴)による懲戒解雇
Q.採用した従業員に犯罪歴があることが判明しました。この者を懲戒解雇することはできるのでしょうか?
A.経歴詐称を理由に懲戒解雇するためには、本人が従事する業務内容や同僚となる従業員との関係で、その犯罪歴が無視できないほど重大なものであることを要すると考えられています。したがって、解雇するためには、①どのような犯罪歴であるか、②それが、会社の業務にどのような支障をもたらすものであるか、を具体的に考える必要があります。
どのような犯罪歴であるかを全く考慮せず、「過去に犯罪歴があるから」との理由だけで懲戒解雇に踏み切ると、裁判で懲戒解雇の有効性が争われた場合、会社が敗訴する可能性(=懲戒解雇が無効と判断される可能性)があります。
就業規則の規定(経歴詐称が懲戒解雇事由となっているか?)
経歴詐称を理由に懲戒解雇できるかを検討するにあたり、まずは、就業規則上、経歴詐称が懲戒解雇事由となっているかを確認してください。多くの会社の就業規則には、懲戒解雇事由として、「重要な経歴を偽って採用されたとき」など、経歴詐称を解雇事由とする旨の規定があると思います。
これは、経歴を詐称して採用された人物を懲戒解雇できる内容の規定です。このような規定があれば、経歴を詐称した人物を解雇できる可能性があります(ただし、後述するように、このような規定があっても解雇できない場合もありますので、ご注意ください。)。
以上に対し、そのような規定が存在しない場合には、経歴詐称を理由とする懲戒解雇はできないと考えられます。
犯罪歴と懲戒解雇とのバランス(社会通念上相当な処分といえるか?)
就業規則に「経歴詐称があった場合、懲戒解雇できる」という規定がある場合、この規定に基づき、経歴詐称した人物を懲戒解雇することができるか否かを検討することとなります。
会社の側から考えてみると、応募者に犯罪歴があるか否かは、採否を判断するにあたり、非常に重要な要素となります。例えば、窃盗・詐欺・横領といった財産犯の前科がある場合、そのような人物を金銭や商品を管理する仕事は任せられないと考えるでしょう。また、性犯罪歴がある場合、同僚(特に、異性の従業員)の中には、一緒に働きたくないと考える人も出てくるでしょう。
したがって、犯罪歴があることは、企業が応募者を採用するか否かを判断するにあたり、重要な判断要素になるといえます。
他方で、中途採用した人物(40~50代)が、10代であった当時に万引きで補導された過去があったとします。中途採用された後の仕事ぶりも真面目で、特段の問題も認められないにもかかわらず、面接時に過去の犯罪歴(補導歴)を説明しなかったとして懲戒解雇することは、客観的にみて、厳しすぎる処分と判断される余地があります。
また、過去に交通事故(人身事故)を起こし、執行猶予判決を受けた人物を中途採用したとします。ほかに前科前歴がなく、また、運転手として採用した等の事情がなければ、面接時に上記犯罪歴を申告しなかったことを理由に経歴詐称があったとして懲戒解雇することは、厳しすぎると判断される可能性があります。
以上のとおり、過去の犯罪歴につき、経歴詐称を理由に懲戒解雇するためには、本人が従事する業務内容や同僚との関係で、その犯罪歴が無視できないほど重大なものであることを要するといえます。そのような内容ではないにもかかわらず、「過去に犯罪歴があったこと」のみを理由に懲戒解雇した場合、その解雇は社会通念上相当性を欠く(すなわち、「処分が厳しく、やり過ぎである」)として、解雇無効と判断される可能性があります(解雇権の濫用。労働契約法16条)。
採用時の注意点
仮に、採用面接の際、犯罪歴の有無を確認していなかった場合、応募者(=採用された人物)は、過去の犯罪歴を質問されなかったため申告しなかったに過ぎないことになります。この場合、後日、犯罪歴が明らかになったとしても、会社は、「従業員が犯罪歴について経歴詐称した。」と主張することができなくなる可能性があります。したがって、採用時には、過去の賞罰(犯罪歴を含む)について、確認することが必要です。
職歴に空白期間がある場合には、空白期間となっている理由や空白期間直前の会社を退職した理由を質問する必要があります。ここでの回答が曖昧であったり、おかしな内容であったりした場合には、何らかの問題が存在する可能性があります。これらについて質問することは、問題を抱える応募者をスクリーニングする効果があり、採用後のトラブルを回避する一助となります。また、採用面接におけるやりとりは、後日、経歴詐称が判明した場合、懲戒解雇の有効性を補強する事情として活用できる可能性があります。
【関連ブログ】
懲戒処分で問題となる「弁明の機会」について
「公正な採用選考をめざして」の概要説明

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
「公正な採用選考をめざして」の概要説明
人手不足に悩む会社
人手不足に悩む会社が増えています。人手不足を解消するため、会社は新卒採用や中途採用に注力しています。その一環として、新卒社員の初任給を大幅にアップする会社(特に、大企業)が出てきています。その一方で、社員がすぐに辞めてしまう、問題社員の対応など、労務問題に悩まされる会社も多くあります。
「よい人材を採用し、定着してもらうこと」は、これまで以上に重要な経営問題となり、採用活動の重要性は増すばかりです。
今回は、従業員の採用に関連して、厚生労働省が定める「公正な採用選考をめざして」の概要をご説明します。
「公正な採用選考をめざして」とは?
「公正な採用選考をめざして」とは、会社における従業員の採用選考に関し、厚生労働省の考え方が示されたものです。法律ではないので、これに違反したからといって、ただちに違法となるわけではありません。もっとも、「公正な採用選考をめざして」に記載された内容は、労働組合法などの個別の法律と重なる部分があるため、これらの法律に違反する可能性があります。
「公正な採用選考をめざして」の基本的な考え方とは?
「公正な採用選考をめざして」では、雇用主にも採用方針・採用基準・採否の決定など、「採用の自由」が認められるとしつつ、その一方で、「採用の自由」は、応募者の基本的人権を侵してまで認められるものではなく、労働者の採用選考に当たっては、応募者の基本的人権を尊重することが重要であるとしています。
そして、雇用主は、応募者に広く門戸を開いた上で、本人の適性と能力に基づいた基準による公正な採用選考を行うことが求められているとしており、就職差別につながるおそれがある事項として、次の14項目を挙げています。
【本人に責任のない事項の把握】
① 「本籍・出生地」に関すること
② 「家族」に関すること(職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産など)
③ 「住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)
④ 「生活環境・家族環境など」に関すること
【本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握】
⑤ 「宗教」に関すること
⑥ 「支持政党」に関すること
⑦ 「人生観・生活信条など」に関すること
⑧ 「尊敬する人物」に関すること
⑨ 「思想」に関すること
⑩ 「労働組合(加入状況や活動歴など)」、「学生運動などの社会活動」に関すること
⑪ 「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること
【採用選考の方法】
⑫ 「身元調査など」の実施
⑬ 「本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類」の使用
⑭ 「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施
最近は、勤務先に「ワークライフバランス」や「コンプライアンス」を求める人が増えているので、「公正な採用選考をめざして」に基づいて採用選考を行うことは、応募者に対し、「しっかりとした会社」であるとの印象を与え、採用活動によい結果をもたらす可能性があります。
その一方で、せっかく採用した社員がすぐに辞めてしまう、採用した社員が問題行動を起こす等の労務問題に直面する会社もあります。そこで、「公正な採用選考をめざして」を遵守しつつ、できる限り、問題のない人材・自社の社風に合った人材を採用したいと思うのが企業の本音と思います。
このようなニーズを満たすためには、「公正な採用選考をめざして」の内容を正しく理解し、同基準が何を求め、どこまでは求めていないかを見極め、それに沿った面接・選考を行うことが必要です。
【関連記事】
中途採用者の解雇(中途採用時の注意点)

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
定年後再雇用者の労働条件(給料など)の決め方
定年後再雇用(継続雇用)の労働条件は、会社が自由に決めることができるのでしょうか?
今回は、従業員を定年後再雇用する場合に、どのような労働条件を設定することができるかについて、ご説明します。
労働条件の提示に関する原則
定年後再雇用は、定年後の新たな労働契約の締結となります。契約は、当事者の合意によって成立するため、どのような労働条件で採用するかにつき、必ずしも労働者の希望に沿う必要はありません。
この点について、厚生労働省のホームページにある「高年齢者雇用安定法Q&A」にも、「高年法が求めているのは、継続雇用制度の導入であり、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではな」いと記載されています(高年齢者雇用安定法Q&AのQ1-9)。
もっとも、労働条件の提示が全くの自由かというと、そうではありません。定年後再雇用(継続雇用)は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年法)に基づく雇用確保措置の一つです。このため、定年後再雇用の労働条件は、会社が自由に設定できるわけではなく、高年法の趣旨を尊重しなければなりません。
高年齢者雇用安定法Q&A(Q1-9)は、「事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年法違反となるものではない。」としています。これを反対解釈すると、高年法は、事業主に対し、合理的な裁量の範囲内での労働条件の提示を要求しているといえます。
それでは、「合理的な裁量の範囲内」とは、どのようなものでしょうか?
この点について参考となる裁判例として、「トヨタ自動車事件」(名古屋高裁平成28.9.28)と「九州惣菜事件」(福岡高裁平成29.9.7)があります。
トヨタ自動車事件(名古屋高裁平成28.9.28)
事務職に従事してきた従業員に対し、定年後再雇用の職種として清掃業務を提示したことを違法と判断した裁判例です。違法と判断した理由は、次のとおりです。
① 定年後の継続雇用として、どのような労働条件を提示するかについては、会社に一定の裁量がある。ただし、提示した労働条件が、到底容認できないような低額の給与水準であること、社会通念に照らし当該労働者にとって到底受け入れがたい職務内容など、実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない場合には、高年法の趣旨に反して違法となる。
② 会社が提示した業務内容は、それまでの職種に属するものとは全く異なった単純労務職としてのものであり、原告がいかなる事務職の業務についてもそれに耐えられないなど通常解雇に相当するような事情が認めれない限り、違法である。
この裁判例は、従業員を定年後再雇用(継続雇用)する際、その職務内容にも配慮しなければならないことを示唆する内容です。
もっとも、「(被告は)我が国有数の巨大企業であって事務職としての業務には多種多様なものがあると考えられるにもかかわらず、(中略)清掃業務等以外に提示できる事務職としての業務があるか否かについて十分な検討を行ったとは認め難い。」と判示しており、裁判所が違法と判断したのは、被告となった会社の企業規模も相当程度影響していたものと考えられます。
九州惣菜事件(福岡高裁平成29.9.7)
定年後再雇用者を時給制のパートタイム勤務とすることで、定年前と比較して大幅な賃金引下げを伴う労働条件の提示(定年前の25%)が違法と判断されました。違法と判断した理由は、次のとおりです。
① 労働者である高年齢者の希望・期待に著しく反し、到底受け入れ難いような労働条件を提示する行為は不法行為となり得る。継続雇用制度は、定年前後における労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることを原則とすべきであり、例外的に継続性・連続性が欠ける労働条件の提示が許容されるためには、合理的な理由が必要である。
② 原告の賃金を月収ベースで比較すると、定年前の約25%に過ぎない。このような大幅な賃金の減少を正当化する合理的な理由が必要であるが、正当化する合理的理由は存在しない。
合理的な裁量を逸脱する場合とは?
これらの裁判例をみると、合理的な裁量の範囲を逸脱する場合として、①著しく低額な賃金を提示する場合、②職務内容の大幅な変更を伴う場合が考えられます。
もっとも、「職務内容の大幅な変更」については、企業規模や人員構成によっては必ずしも合理的な裁量を逸脱したとはいえない場合もあり得ると考えます。具体的には、企業規模・人員構成、業務の属人化防止、スタッフの若返り等の理由から、定年後再雇用に伴って職種を大きく変更することにつき、やむを得ない理由がある場合には、合理性が認められる可能性もあると思います。
定年後再雇用時に従業員の職務内容の変更を希望する場合には、定年前から適性に関する資料・証拠を集めておくとともに(「従前の職務に従事させることが相当ではないこと」の証拠)、定年前の人事考課の結果、会社規模、対象業務の人員状況等を踏まえ、対象者と十分に協議し、了承が得られるよう努めることが必要となります。
「賃金の低下」に関し、「定年前の賃金の○%以下であれば違法」という明確な基準はありません。
提示額が合理的な裁量の範囲内であるかは、提示する労働条件(労働日、労働時間、業務内容、業務の難易等)を踏まえ、個別具体的に判断することになります。職務内容を変更するとともに、これに伴って労働日・労働時間を減らす場合には、賃金の減額提示も合理性があると考えられます。もっとも、九州惣菜事件が「25%は違法」と判断したことを踏まえますと、最低ラインとして、25%を下回らないよう配慮するのがよいでしょう。

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
休職中の従業員からの育児休業の申出を拒否できるか?
休職中の男性従業員から、育児休業の申出がありました。育児休業とは、仕事を休んで子育てに専念してもらうための制度であり、休職中の従業員に認める必要はないのではないかと思います。休職中の従業員からの育児休業の申出を拒否することはできるのでしょうか?
結論から述べますと、休職中であることを理由に育児休業の申出を拒否することはできないと思われます。
育児休業は、1歳未満の子を養育する労働者であれば取得することができます。労使協定によって育児休業を認めない従業員を定めることができますが、法律上、そのような従業員は、①雇用された期間が1年に満たない者、②育児休業の申出日から1年以内に雇用契約が終了することが明らかな者、③1週間の所定労働日数が2日以下の者に限定されています。このため、休職中の従業員を育児休業の対象外とすることは認められていません。
したがって、たとえ従業員が休職中であったとしても、育児休業の申出があれば、これを会社が拒否することはできないと考えます。
なお、育児休業と休職は別の制度であるため、育児休業期間中も休職期間は進行することになります。このため、育児休業期間中に休職期間の満了日を迎えるケースも想定できます。
もっとも、育児休業期間中に休職期間が満了しても、育児休業期間中は労働義務がないので、その従業員に対し、休職期間が満了したことを理由に復職を命じることはできません。よって、休職期間満了時に復職していないとして、その従業員を解雇(退職扱い)することはできません。
このような場合、休職期間満了時に復職の可否を検討し、復職不可と判断した場合には、育児休業期間が終了した時点で解雇(退職扱い)とすることも考えられます。
育児休業と休職が別の制度であることを踏まえると、このような対応が違法と評価されることはないと思われますが、対象となる従業員の反発を招き、トラブルとなる虞があります。そこで、このような場合には、休職期間の終期を「育児休業が終了した時点」まで延長し、その時点で復職の可否を判断し、その従業員の処遇を決定することも検討すべきと考えます。
もっとも、このような結論は、他の休職者との公平に反するように思われます。この点については、育児休業期間が終了するまで休業期間を延長することは、育児休業を取得したことに伴うものであり、育児休業が法律上の制度であることを踏まえると、これにより他の休職者との間に差異が生じたとしても、一定の合理的理由があるといえるのではないかと考えます(とはいえ、非常に悩ましい問題です。)。
【関連ブログ】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
会社が負担した資格取得費用を返してもらえるか?
Q.当社には、資格取得を希望する従業員に対し、その取得費用を会社が負担する制度があります。もっとも、資格取得後、すぐに辞められては困るので、3年以内に退職した場合には、会社が負担した費用を返還してもらうことになっています。先日、この制度を利用した従業員から退職の申出がありました。資格取得後、数か月しか経過していなかったため、資格取得費用の返還を求めたところ、その従業員から、労働基準法に違反していると言われました。そのようなことはあるのでしょうか?
従業員のモチベーションアップを図るため、資格取得を奨励し、その費用を負担しようとする会社が増えています。その一方で、上記のような問題で困っている会社もあります。そこで、今回は、資格取得費用の返還について説明します。
従業員に対する資格取得費用の返還請求では、労働基準法16条に違反するか否かが問題となります。
労働基準法16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
過去の裁判例を分析しますと、「会社による資格取得費用の負担が、従業員に対する貸付であり、一定期間労働した場合に返還義務を免除する特約を付したもの」といえる場合、上記のような請求は、労働基準法16条に違反しないと考えられます。
それでは、どのような場合が「会社の労働者に対する貸付」といえるかですが、この点は、① 従業員が自主的に資格取得制度を申請したか、② 取得した資格に汎用性があるか(他社でも活用できるか)がポイントとなります。
従業員が自主的に資格取得制度を申請したか
従業員が自主的に資格取得制度を申請した場合には、従業員は、その自由意思で会社から資格取得費用を借り受けたといえます。これに対し、会社が資格取得を命じた場合、従業員は業務命令に従って資格を取得したことになります。この場合、資格取得費用は会社が負担すべきものであり、たとえ資格取得制度を利用したとしても、その費用につき、会社の労働者に対する貸付とみることは困難といえます。
なお、実務上の注意点として、労働者が自主的に資格取得制度を利用したというためには、資格取得制度を利用するか否かは従業員の自主判断による旨を規程上明記すべきです(そして、実際に、どのような資格を取得するか、どのような専門学校を利用するかは、従業員の選択に委ねることになります。)。また、規程上、資格取得費用の貸付であることも明記しておく必要があります。
資格取得制度を利用するにあたっては、資格取得制度の具体的内容が記載された書面を交付するとともに、貸付額や返還条件が記載された貸付契約書(金銭消費貸借契約書)や誓約書などの書面を取り交わしておくことが必要です。
取得した資格に汎用性があるか
取得した資格に汎用性があり、転職活動で有利となるもの(簿記、運転免許、危険物取扱者など)については、自社の業務遂行に有用な面はありますが、それ以上に、取得した従業員の利益になるといえます。この場合、労働者は、自らの市場価値を高めるために資格取得を目指し、その取得費用を会社から借り受けたと評価される可能性が高いといえます。例えば、運送業における大型車両の免許など、それがないと大型車両の乗務に従事できませんが、同業他社でも活用できる資格であるため、その取得費用は、従業員個人のスキルアップのための費用であり、本来であれば労働者が自己負担すべき性質のものといえるでしょう。
これに対し、他社での有用性が限定的な資格は、実質的にみれば、その会社の業務に従事するために取得するものであり、業務性が高いといえます。そして、そのような資格取得にかかる費用は、社内研修に準じて、会社が負担すべき費用と考えることができます。したがって、その費用を会社から労働者に対する貸付とみることは困難ではないかと思われます(もっとも、実際は、そのような資格は稀であろうと思われます。)。
以上のとおり、従業員が自主的に資格取得制度を利用し、取得した資格に汎用性がある場合、退職時に取得費用の返還を請求しても、労働基準法16条には違反しないと考えられます。
これに対し、会社が従業員に資格取得を命じた場合、取得した資格が他社での有用性が限定的である場合、その取得費用は会社が負担すべきものといえます。これを従業員の退職時に貸付金の返還という形式で請求することは、従業員の退職を契機として、本来であれば同人が負担する必要のない費用を請求するものであり、労働基準法16条に違反すると判断されるものと考えられます。
参考裁判(東京地判令和5年10月26日。労働経済判例速報2554号31頁)
自動車教習事業を営む会社が、元従業員に対し、在職中に教習指導員資格を取得するための費用に関する準消費貸借契約に基づき返還請求した事件において、裁判所は、立替費用の返還請求は労働基準法16条には違反しないと判断しました(東京地判令和5年10月26日。労働経済判例速報2554号31頁)。
この事件では、従業員が教習指導員資格を取得するための費用を会社が立て替え、会社と従業員が、①その立替分を消費貸借の目的とすること、②資格取得後3年が経過する前に退職する時は退職までに貸付金を返還しなければならないこと、③従業員が3年を超えて勤務し続けた場合には貸付金の返還を免除することを内容とする「免除特約付準消費貸借契約」を締結していました。
そして、同契約に基づく立替費用の返還請求が労働基準法16条に違反しないかが争われましたが、裁判所は、以下を理由に、労働基準法16条に違反しないと判断しました。
① 教習指導員資格は国家資格であり、従業員個人に帰属するものであるから、本来であれば資格取得者である従業員個人が負担すべきものといえる。
② 自動車教習所という限られた業界内であるものの転職活動等で有利になるものであり、従業員は、当該資格の取得によって利益を得たといえる。
③ 貸付額は47万9700円であり、教習指導員資格を得て会社(原告)で稼働すれば、毎月3万円の手当てが得られることから、投下した資本について比較的早期に回収することができる。
④ 従業員は、教習指導員資格を取得することを希望するとともに、それを前提として会社と雇用契約を締結したと認められる。
⑤ 返還免除に要する3年間という期間についても特段長期にわたるとはいえない。
この裁判例も、取得した資格が従業員個人に利益をもたらすものであること、従業員が資格取得を希望したことを重視して、労働基準法16条に違反しないと判断したものと思われます。

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
中途採用者の解雇(中途採用時の注意点)
人手不足が深刻化している現代。即戦力となることを期待して採用した社員が、期待していた結果を出してくれない・・・。このような場合、能力不足を理由に解雇することは可能でしょうか。
まずは結論ですが、「期待していた結果を出してくれなかった」との理由で中途採用者を解雇することは、原則として難しいと考えます。
就業規則には、解雇事由として「勤務成績が著しく不良であること」が記載されているのが通常です。「期待していた結果を出してくれなかった」というのは、「勤務成績が著しく不良であること」に該当するようにも思われます。
しかし、解雇が認められるためには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当であること」が要求されます(労働契約法16条)。そして、「期待していた結果を出したか否か」は抽象的であり、人によって評価が分かれてしまいます。特に、解雇事由として「勤務成績が著しく不良であること」と定められている場合、「期待していた結果を出してくれない」ことが、「勤務成績が著しく不良」を当然に意味するとは限りません。このため、裁判になった場合、「客観的に合理的な理由」があるとは認められず、解雇が無効と判断される可能性が高いと考えます。
このような事態を回避するためには、採用時に工夫することが必要です。
例えば、採用時、①どのようなスキルや能力を評価して採用するのかを明らかにしておく、②「会社が期待する結果」がどのようなものであるかを提示しておくことが有用です。特に、後日のトラブルを回避するために、「会社が期待する結果」は、定量的なものであることが望ましいでしょう。
また、高い地位や高収入で採用した場合、会社は、その人を「高度なスキルを有するプロフェッショナル」として採用したことが推測できるため、能力不足を理由とする解雇の有効性を補強する材料になるといえます。
実際に解雇する場合には、解雇が「社会通念上相当であること」も要求されます。このため、「期待していた結果を出してくれなかった」が客観的に証明可能であったとしても、いきなり解雇するのではなく、本人と面談して、改善の機会を与える等の措置を講ずることが必要です。
【関連記事】
退職勧奨の進め方(事前準備・面談時の注意点)【会社向け】
退職勧奨の切り出し方(想定問答)【会社向け】
懲戒処分で問題となる「弁明の機会」について

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
懲戒処分で問題となる「弁明の機会」について
懲戒処分を行うにあたり、対象者(社員本人)に「弁明の機会」を与えるか、どのようなタイミング・方法(書面・口頭)で「弁明の機会」を付与すればよいかわからないとのご相談を受けます。
懲戒処分の有効性が争われる裁判(労働審判)では、労働者側から「弁明の機会がないまま懲戒処分を受けた。このような懲戒処分は無効である。」と主張されるケースも多く、懲戒処分を進めるにあたり、「弁明の機会」は非常に重要となります。
そこで、今回は、弁明の機会の付与について、実務上の注意点を説明します。
【関連記事】
退職勧奨の進め方(事前準備・面談時の注意点)【会社向け】
退職勧奨の切り出し方(想定問答)【会社向け】
弁明の機会とは
そもそも「弁明の機会」とは、いったい何でしょうか?
いつ、何を行えば、「弁明の機会を与えた」といえるのでしょうか?
弁明の機会とは何であるか?
「弁明の機会」とは、懲戒処分に先立ち、対象者(社員本人)から、問題行動に及んだ理由・動機、問題行動を起こしたことに対する現時点での考え(反省など)を聞く機会を設けることです。
簡単にいえば、「問題を起こした本人の言い分を聞く。」ということです。
会社は、対象者の言い分も聞いた上で、①懲戒処分を行うか否か、②(処分するとして)どのような懲戒処分とするかを判断します。
弁明の機会を与える理由は?
どうして弁明の機会を与える必要があるのでしょうか?
これは、懲戒処分の性質にかかわってきます。すなわち、懲戒処分とは、企業秩序を維持するための制裁罰と言われています。実社会における刑罰のようなものです。このような懲戒処分の性質上、その処分内容には相当性が要求されます(労働契約法15条)。
労働契約法15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
会社は、懲戒処分が「社会通念上相当である」というために、問題行動の内容(行為態様、結果の重大性、反復継続性など)のほか、行為に至った動機や反省の有無など、問題行動をめぐる様々な事情を総合した上で、懲戒処分を決定しています。そして、「弁明の機会を通じて明らかとなった本人の言い分も考慮して処分内容を決定すること」は、懲戒処分の相当性を裏付ける事情の一つとなります。
弁明の機会を与える「もう一つの理由」
実務では、対象者に弁明の機会を与え、その言い分を聞くことは、「ガス抜き」としての性質もあります。対象者の言い分を聞くことで、無用なトラブル(裁判など)に発展することを防止する意味もあります。
弁明の機会は、必ず与えないといけないのか?
就業規則に規定がある場合
この場合、弁明の機会を与えないといけない
就業規則上、「(懲戒処分を行うためには)弁明の機会を与えなければならない。」と規定されている場合には、弁明の機会を設けることが必須です。もし弁明の機会を与えていないと、その懲戒処分は就業規則に違反していることとなり、当該処分そのものが無効となってしまいます。
このような主張は、後日、懲戒処分が裁判(労働審判)等で争われた場合、従業員側から主張されることが多いといえます。このため、懲戒処分を実施する場合には、就業規則上、弁明の機会を与えることが要求されているか否かの確認が必要です。
弁明の機会を与える時期(通告時に聞けばよいのか?)
弁明の機会は、懲戒処分に先立って付与するものです。このため、懲戒処分の通告時に本人の言い分を聞いたとしても、それでは弁明の機会を与えたとはいえないので、ご注意ください。また、懲戒処分の通告前に弁明の機会を与えたとしても、懲戒処分通告と同じ日時・場所に実施すると、「弁明の機会を与えられなかった。」と主張される虞があります。
そこで、「弁明の機会を与えること」と「懲戒処分の通告」は別個に行うべきといえます。
弁明の機会を与える時期(事情聴取時に聞けばよいのか?)
事情聴取の際、事実上、本人の言い分を聞くことがあります。ただ、この場合も、後日、「事情聴取は受けたが弁明の機会は与えられなかった。」と主張される虞があります。このため、無用な紛争を回避するためにも、就業規則上、弁明の機会の付与が要求される場合には、「事情聴取」と「弁明の機会を与えること」を別個に行うべきといえます。
就業規則に規定がない場合
この場合、弁明の機会を与えないといけないわけではない
就業規則上、「(懲戒処分を行うためには)弁明の機会を与えなければならない。」との規定がない場合、弁明の機会を与えていないからといって、それを理由に懲戒処分が無効となることはありません。
そうであっても弁明の機会を与えた方がよい理由
懲戒解雇や降格処分など、重い処分を考えている場合には、就業規則上、弁明の機会を付与することが要求されていないとしても、弁明の機会を与えておくべきです。
これは、重い処分を与える場合には、就業規則に規定がなくても弁明の機会を与えるべきとする見解があるため、後日、裁判等になった場合、相手方弁護士から、このような主張を受ける可能性があるからです。また、弁明の機会を与えることは、前述した「ガス抜き」としての効果が期待できることも理由です。
その他の注意点(書面で通知しておくこと)
裁判や労働審判で、「弁明の機会を与えた/与えていない」が争点となることは、少なからずあります。
このような場合に備えて、対象者には、弁明の機会を与える旨の書面(通知書)を交付しておくことは有益です。同書面には、問題行動の概要を記載した上で、これに対する弁明の機会を与えること(その日時)を明記しておいてください。懲戒解雇など、後日、紛争となる可能性が高いケースでは、このような慎重な対応が必要です。
裁判では、証拠の有無が重要です。「本人には、弁明の機会を与えると口頭で伝えた。」では、証拠がないため、会社側の言い分が認められない可能性があります。そのような可能性をなくすためにも、書面の交付は重要です。
【関連記事】
退職勧奨の進め方(事前準備・面談時の注意点)【会社向け】
退職勧奨の切り出し方(想定問答)【会社向け】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
パワハラを理由とする懲戒処分の注意点
パワハラ問題が発生した場合、企業秩序を維持するため、加害者を処分(懲戒処分)することが考えられます。今回は、パワハラの加害者に対する懲戒処分の程度について説明します。
【関連記事】
セクハラ・パワハラ問題への対処法
パワハラの判断基準(簡易版)
懲戒処分で問題となる「弁明の機会」について
注意指導が行き過ぎたケース
注意指導が行き過ぎたケースは、その方法(過剰な叱責など)に問題はあるものの、注意指導しなければならない場合であり、業務上の必要性は一応あったといえます。この場合、行為態様・行為期間を総合して、厳重注意や軽い懲戒処分(戒告、減給など)の中から選択することになります。また、注意指導が行き過ぎたケースであっても、過剰ないし執拗な注意指導によって被害者が精神疾患に陥った場合には、より重い懲戒処分を検討することになります。
なお、加害者が管理職の立場にあり、同種行為を繰り返す場合には、人事権行使としての降格(降職)を検討することになります。
業務上の必要性のないパワハラ(職場いじめなど)
業務上の必要性のないパワハラは、悪質性が高いといえます。このような場合には、行為態様、行為期間や被害態様等を勘案した上で、減給や停職を検討することになります。
刑事事件(傷害事件など)に該当するようなパワハラ
業務上の必要性の有無にかかわらず、その行為態様が刑事事件に該当する場合には、再発防止の観点から厳しい態度で臨む必要があります。この場合、行為態様や被害状況(被害者の負傷程度など)によっては懲戒解雇も検討することになります。
【関連記事】
パワハラの判断基準(簡易版)
懲戒処分で問題となる「弁明の機会」について

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。