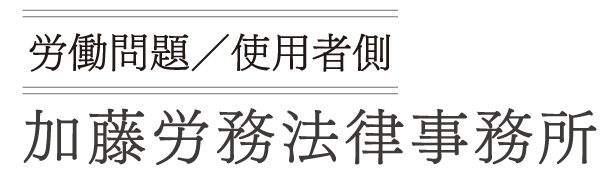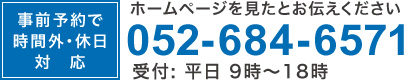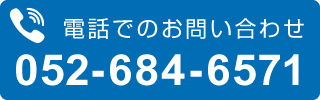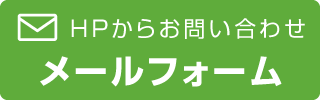解雇や残業代請求などを理由に、労働者が会社に対し、労働審判を起こすケースが増えています。労働審判の呼出状は、ある日、膨大な書類とともに、裁判所から届きます。呼出状が届いてから、第1回期日まで、1か月程度しか残っていません。突然のことに、驚き、戸惑いますが、時間は待ってくれません。冷静になって、できることを一つずつ実行しましょう。
このページの目次
労働審判の流れ
「労働審判」は、裁判と同じようで異なります。まずは、労働審判の特徴を押さえておくことが重要です。
そもそも労働審判とは、労働者と使用者との間における労働トラブルを解決するための裁判手続きですが、その本質は、裁判所が間に入って、和解解決に向けた話し合いを行う点にあります。したがって、労働審判の対応を準備する際には、労働者の主張に対する反論だけではなく、会社として、どのような和解であれば応じられるかを十分に考えておく必要があります。
具体的には、第1回の労働審判期日に先立ち、「労働審判申立書」に記載された労働者の請求(例:「不当に解雇されたので、労働者としての地位の回復を求める」、「残業代を支払ってくれないので、残業代を支払ってほしい」など)に対し、会社が反論していくことになります(例:「解雇には、十分な合理的理由がある」、「解雇ではなく合意退職である」、「残業代は支払っている」、「労働者が主張する残業代の計算方法は間違っている」など)。そして、このような反論準備に加えて、和解するのであれば、どのような条件を提案・希望するかを考えておく必要があります(例:「解雇の場合、金銭解決を希望する」、「残業代請求の場合、労働者の請求額の50%を支払う」など)。
労働審判期日では、会社と労働者が事前に提出した資料に基づき、裁判所が双方に対し、事実関係について質問します(1~2時間程度)。裁判所は、反論書に書いていないことや細かい事実関係を質問することが多いので、事実関係の詳細を知る関係者(上司、同僚など)には、労働審判期日に裁判所へ来てもらえるよう、スケジュールを調整しておくことが必要です。また、労働審判の本質は、和解に向けた話し合いです。このため、解決金の金額などについて裁量のある決裁者(社長、人事部長など)も労働審判期日に出席できるよう、スケジュールを調整することも必要です(決裁者が裁判所へ来れない場合には、当日、携帯電話で連絡がとれるようにしておく必要があります。)。労働審判期日への関係者と決裁者の出席は必須です。
労働審判は、短期間での和解解決を目指す制度です。具体的には、3回以内の期日(話し合い)での和解解決を目指します。このため、裁判所は、第1回の労働審判期日において、和解案を提示します。第1回の労働審判期日は、3時間程度と長時間に及ぶものですが、①事実関係の質問、②和解に関する意向の聴取、③和解案の提示と、かなり凝縮されたものとなります。
なお、和解できない場合には、裁判所が結論を下します(「審判」といいます。)。審判とは、当事者双方の主張や証拠に基づいて、審判官(裁判官)が紛争に対する法的判断を行うものです(審判に不服がある場合、不服を申し立て、裁判に移行させることが可能です。)。
労働審判では、第1回期日において、和解案が提示されるのが通常です。
労働審判で弁護士に依頼すべき理由
労働審判は、和解解決に向けた話し合いの場所となります。このため、労働者から労働審判を申し立てられた場合、「話し合いの手続きだから弁護士に依頼しないで自分達で解決しよう」、「準備する時間がなかったから、第2回期日でしっかりと反論しよう」などと考える会社もあります。
しかし、そのような対応は危険です。
労働審判は、制度上、3回の期日が予定されています。しかし、実際は、第1回期日で裁判所から和解案が提示されます。このため、会社は、事前準備をしっかり行った上で、第1回期日に臨む必要があります。労働者は十分に準備した上で労働審判を申し立てていますので、会社側の準備が不十分ですと、会社にとって不利な和解案が提示される危険があります。
また、話し合いが決裂した場合には、裁判所が結論を下すことになりますが、その場合も、会社の主張や証拠の提出が不十分であれば、労働者側に有利な結論となってしまう危険があります。
弁護士がついていれば、当初の段階から貴社の主張を法的に整理し、これを裏付ける立証方法を検討することが可能です。話し合いの席上でも、裁判所の理解が得られるよう説得し、少しでも貴社に有利な内容で合意できるよう対応いたします(法律論を押さえた説明でないと、裁判所の理解を得ることはできません。)。
話し合いが決裂してから主張や証拠を整えようとしても遅いので、当初の段階から綿密な準備を行う必要があります。
労働審判に関するご相談・お問い合わせ
労働審判に関するご相談・お問い合わせは、こちら(お問い合わせのページ)までお願いします。
加藤労務法律事務所が過去に取り扱った労働審判として、例えば、以下の事案があります(いずれも会社側の代理人として、最終的には円満解決しました。)。
① 懲戒処分の有効性が争われた労働審判
② 懲戒解雇の有効性が争われた労働審判
③ 内定取消が争われた労働審判
労働審判の弁護士費用
| 事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
| 労働審判 | 330,000円~ | 330,000円~ |
| 民事訴訟 | 550,000円~ | 550,000円~ |
※いずれも消費税を含んだ金額です。
※実費(コピー代、切手代、交通費など)は別途いただきます。
※労働審判事件から民事訴訟事件に移行した場合、差額を追加着手金としてご請求します。
例)労働審判から民事訴訟に移行
550,000円-330,000円=220,000円
【関連ブログ】
労働審判に関するご相談・お問い合わせは、こちら(お問い合わせのページ)までお願いします。
加藤労務法律事務所では、名古屋において、労務問題でお困りの会社を支援すべく、日々積極的に労働問題に取り組んでおります。そして、会社側代理人として、多数の労働審判事件を取り扱い、解決に導いてきました。
名古屋で従業員との労働トラブルでお悩みの会社経営者、ご担当者様におかれましては、加藤労務法律事務所にご相談ください。