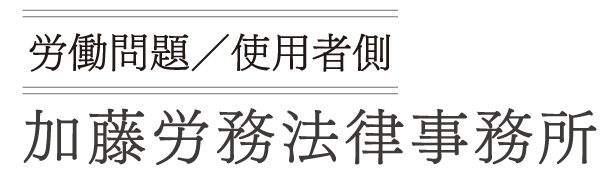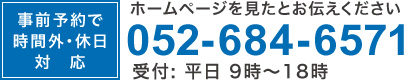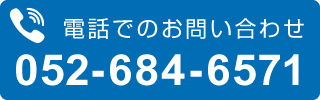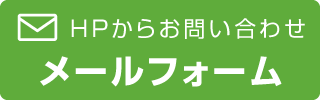会社が安全配慮義務を怠った結果、労災事故が発生した場合には、会社は被災者の損害を賠償しなければならないこととなります。今回は、そのような事態に備えて、労災上乗せ保険(使用者賠償責任保険など)に加入することの必要性について、ご説明します。
1 賠償額の高額化傾向
労災事故が発生した場合には、治療費のほか、休業損害、慰謝料、その他損害(通院交通費など)が損害として発生します。さらに、被災者に後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害に関する損害(逸失利益、後遺障害慰謝料)も損害賠償の対象となります。
特に、後遺障害に関する損害は、将来にわたる損害を補償する性質のものであることから、その損害額は高額となります。具体的には、後遺障害が認定されると、損害額は合計1000万円以上となり、高位の後遺障害が認定された場合には、賠償額が数千万円単位にのぼることもあります。
2 労災保険給付は損害の全部をカバーしないこと
以前にお話しましたとおり、労災保険給付は、被災者の損害の全部をカバーするわけではありません(労災事故における損害賠償リスク【会社向け】)。このため、「労災事故が起こっても、労災保険に加入しているから大丈夫だ。」ということにはなりません。上述しましたとおり、たとえ労災保険給付が支払われたとしても、会社は、1000万円以上(場合によっては、数千万円単位)の自己負担を余儀なくされる場合も十分に考えられるのです。
3 裁判となった場合の問題点
さらに、被災者から、損害賠償金の支払いを求めて訴えられた場合には、事態はさらに深刻となる可能性があります。すなわち、裁判で和解が不調となり、判決となった場合、会社は、上述した単位の賠償金を支払うよう命じられる危険があります。しかも、判決の場合、賠償金を一括して支払うよう命じられるのですが、これを支払うことができない場合には、強制執行を受けることになります。
そして、強制執行では、預金や売掛金を差し押さえられてしまうため、これらを別の支払いに充てることができません。さらに、預金や売掛金が差し押さえられた場合には、銀行からは借入金の一括返済を請求されるリスク、取引先からは信用不安を理由とする契約解除のリスクがあります。最悪の場合、会社は倒産する危険すらあります。
4 まとめ
以上のとおり、労災事故が発生した場合には、会社経営が非常に大きなダメージを受ける危険があります(実際に、労災事故の補償を余儀なくされた結果、資金繰り等の面で、深刻な影響を受けた会社は多数あります。)。このようなリスクを回避・軽減するためには、使用者賠償責任保険など、いわゆる労災上乗せ保険に加入することが有益です。
もし、加入していないのであれば、労災事故リスクの軽減を図るためにも、加入なさることを強くお勧めします(なお、保険の種類や補償内容については、保険会社にお問い合わせください。)。 このようなリスクに備えておくことも、「予防法務」の一環として、とても大切です。
【関連ブログ】
労災による損害賠償請求を受けた場合に、まず行うこと【会社向け】
労災による賠償請求があったときに検討すべきこと(被災者側の減額事由)【会社向け】

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。