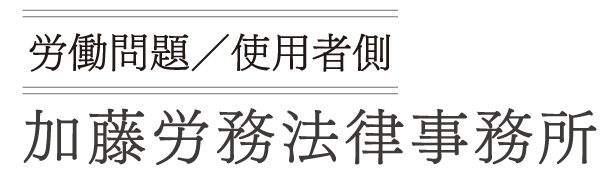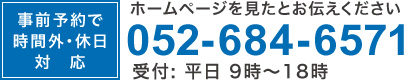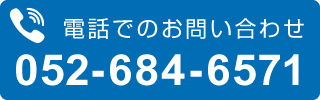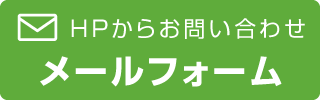Q.当社には、資格取得を希望する従業員に対し、その取得費用を会社が負担する制度があります。もっとも、資格取得後、すぐに辞められては困るので、3年以内に退職した場合には、会社が負担した費用を返還してもらうことになっています。先日、この制度を利用した従業員から退職の申出がありました。資格取得後、数か月しか経過していなかったため、資格取得費用の返還を求めたところ、その従業員から、労働基準法に違反していると言われました。そのようなことはあるのでしょうか?
従業員のモチベーションアップを図るため、資格取得を奨励し、その費用を負担しようとする会社が増えています。その一方で、上記のような問題で困っている会社もあります。そこで、今回は、資格取得費用の返還について説明します。
従業員に対する資格取得費用の返還請求では、労働基準法16条に違反するか否かが問題となります。
労働基準法16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
過去の裁判例を分析しますと、「会社による資格取得費用の負担が、従業員に対する貸付であり、一定期間労働した場合に返還義務を免除する特約を付したもの」といえる場合、上記のような請求は、労働基準法16条に違反しないと考えられます。
それでは、どのような場合が「会社の労働者に対する貸付」といえるかですが、この点は、① 従業員が自主的に資格取得制度を申請したか、② 取得した資格に汎用性があるか(他社でも活用できるか)がポイントとなります。
このページの目次
従業員が自主的に資格取得制度を申請したか
従業員が自主的に資格取得制度を申請した場合には、従業員は、その自由意思で会社から資格取得費用を借り受けたといえます。これに対し、会社が資格取得を命じた場合、従業員は業務命令に従って資格を取得したことになります。この場合、資格取得費用は会社が負担すべきものであり、たとえ資格取得制度を利用したとしても、その費用につき、会社の労働者に対する貸付とみることは困難といえます。
なお、実務上の注意点として、労働者が自主的に資格取得制度を利用したというためには、資格取得制度を利用するか否かは従業員の自主判断による旨を規程上明記すべきです(そして、実際に、どのような資格を取得するか、どのような専門学校を利用するかは、従業員の選択に委ねることになります。)。また、規程上、資格取得費用の貸付であることも明記しておく必要があります。
資格取得制度を利用するにあたっては、資格取得制度の具体的内容が記載された書面を交付するとともに、貸付額や返還条件が記載された貸付契約書(金銭消費貸借契約書)や誓約書などの書面を取り交わしておくことが必要です。
取得した資格に汎用性があるか
取得した資格に汎用性があり、転職活動で有利となるもの(簿記、運転免許、危険物取扱者など)については、自社の業務遂行に有用な面はありますが、それ以上に、取得した従業員の利益になるといえます。この場合、労働者は、自らの市場価値を高めるために資格取得を目指し、その取得費用を会社から借り受けたと評価される可能性が高いといえます。例えば、運送業における大型車両の免許など、それがないと大型車両の乗務に従事できませんが、同業他社でも活用できる資格であるため、その取得費用は、従業員個人のスキルアップのための費用であり、本来であれば労働者が自己負担すべき性質のものといえるでしょう。
これに対し、他社での有用性が限定的な資格は、実質的にみれば、その会社の業務に従事するために取得するものであり、業務性が高いといえます。そして、そのような資格取得にかかる費用は、社内研修に準じて、会社が負担すべき費用と考えることができます。したがって、その費用を会社から労働者に対する貸付とみることは困難ではないかと思われます(もっとも、実際は、そのような資格は稀であろうと思われます。)。
以上のとおり、従業員が自主的に資格取得制度を利用し、取得した資格に汎用性がある場合、退職時に取得費用の返還を請求しても、労働基準法16条には違反しないと考えられます。
これに対し、会社が従業員に資格取得を命じた場合、取得した資格が他社での有用性が限定的である場合、その取得費用は会社が負担すべきものといえます。これを従業員の退職時に貸付金の返還という形式で請求することは、従業員の退職を契機として、本来であれば同人が負担する必要のない費用を請求するものであり、労働基準法16条に違反すると判断されるものと考えられます。
参考裁判(東京地判令和5年10月26日。労働経済判例速報2554号31頁)
自動車教習事業を営む会社が、元従業員に対し、在職中に教習指導員資格を取得するための費用に関する準消費貸借契約に基づき返還請求した事件において、裁判所は、立替費用の返還請求は労働基準法16条には違反しないと判断しました(東京地判令和5年10月26日。労働経済判例速報2554号31頁)。
この事件では、従業員が教習指導員資格を取得するための費用を会社が立て替え、会社と従業員が、①その立替分を消費貸借の目的とすること、②資格取得後3年が経過する前に退職する時は退職までに貸付金を返還しなければならないこと、③従業員が3年を超えて勤務し続けた場合には貸付金の返還を免除することを内容とする「免除特約付準消費貸借契約」を締結していました。
そして、同契約に基づく立替費用の返還請求が労働基準法16条に違反しないかが争われましたが、裁判所は、以下を理由に、労働基準法16条に違反しないと判断しました。
① 教習指導員資格は国家資格であり、従業員個人に帰属するものであるから、本来であれば資格取得者である従業員個人が負担すべきものといえる。
② 自動車教習所という限られた業界内であるものの転職活動等で有利になるものであり、従業員は、当該資格の取得によって利益を得たといえる。
③ 貸付額は47万9700円であり、教習指導員資格を得て会社(原告)で稼働すれば、毎月3万円の手当てが得られることから、投下した資本について比較的早期に回収することができる。
④ 従業員は、教習指導員資格を取得することを希望するとともに、それを前提として会社と雇用契約を締結したと認められる。
⑤ 返還免除に要する3年間という期間についても特段長期にわたるとはいえない。
この裁判例も、取得した資格が従業員個人に利益をもたらすものであること、従業員が資格取得を希望したことを重視して、労働基準法16条に違反しないと判断したものと思われます。