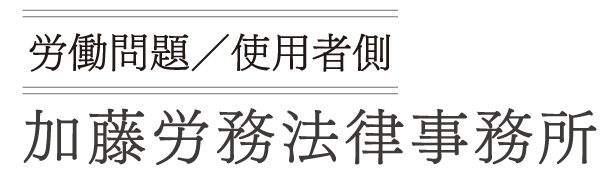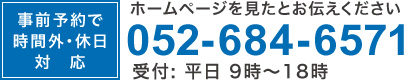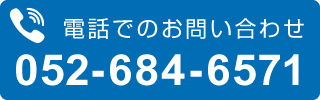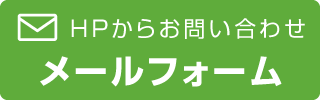パワハラ問題が発生した場合、企業秩序を維持するため、加害者を処分(懲戒処分)することが考えられます。今回は、パワハラの加害者に対する懲戒処分の程度について説明します。
【関連記事】
セクハラ・パワハラ問題への対処法
パワハラの判断基準(簡易版)
懲戒処分で問題となる「弁明の機会」について
このページの目次
注意指導が行き過ぎたケース
注意指導が行き過ぎたケースは、その方法(過剰な叱責など)に問題はあるものの、注意指導しなければならない場合であり、業務上の必要性は一応あったといえます。この場合、行為態様・行為期間を総合して、厳重注意や軽い懲戒処分(戒告、減給など)の中から選択することになります。また、注意指導が行き過ぎたケースであっても、過剰ないし執拗な注意指導によって被害者が精神疾患に陥った場合には、より重い懲戒処分を検討することになります。
なお、加害者が管理職の立場にあり、同種行為を繰り返す場合には、人事権行使としての降格(降職)を検討することになります。
業務上の必要性のないパワハラ(職場いじめなど)
業務上の必要性のないパワハラは、悪質性が高いといえます。このような場合には、行為態様、行為期間や被害態様等を勘案した上で、減給や停職を検討することになります。
刑事事件(傷害事件など)に該当するようなパワハラ
業務上の必要性の有無にかかわらず、その行為態様が刑事事件に該当する場合には、再発防止の観点から厳しい態度で臨む必要があります。この場合、行為態様や被害状況(被害者の負傷程度など)によっては懲戒解雇も検討することになります。
【関連記事】
パワハラの判断基準(簡易版)
懲戒処分で問題となる「弁明の機会」について

名古屋市をはじめ愛知県全域、岐阜・三重・静岡の東海エリアで、使用者側の労働問題に対応する弁護士事務所「加藤労務法律事務所」です。
問題社員への対応、団体交渉、労災事故、残業代請求など、企業経営における労務の悩みは、経営者や人事ご担当者様にとって大きな負担です。
当事務所は、平成14年から一貫して企業側の労働問題に取り組んできた豊富な経験と、「労務」×「賠償」×「交渉」の専門知識を駆使し、円満な解決をサポートします。
私たちは、一方的に争うのではなく、従業員が相手だからこそ配慮ある「和解」を大切にし、早期解決を目指します。
相談しやすい雰囲気の中、専門用語を使わない分かりやすい説明と、状況に応じた密な報告で、貴社の不安に最後まで寄り添います。
労務問題でお困りの際は、一人で抱え込まず、まずは私たちにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。